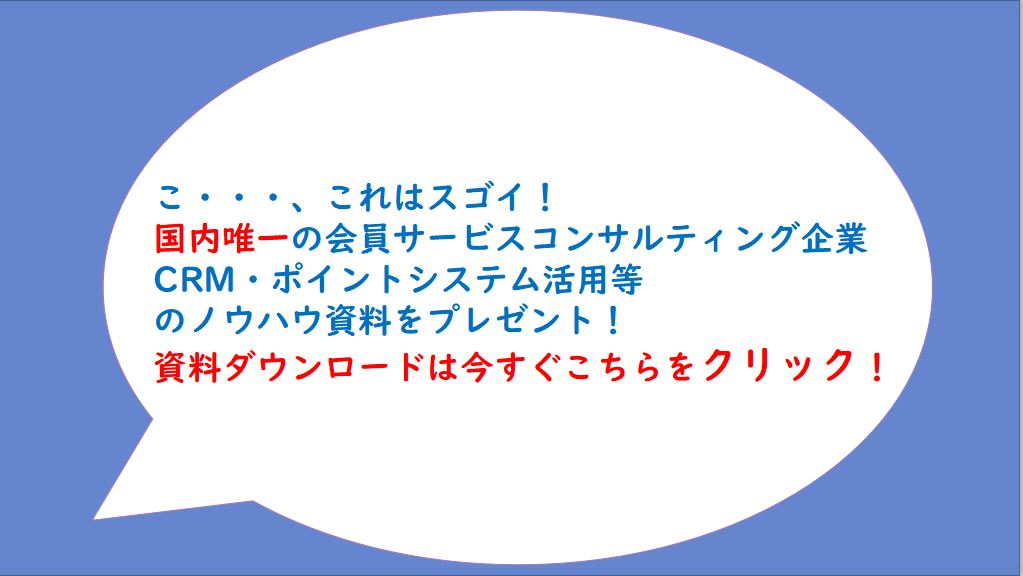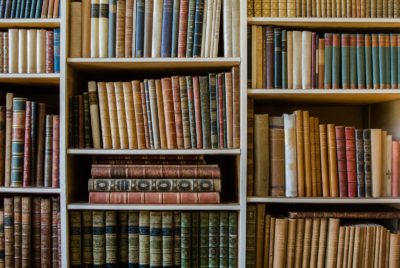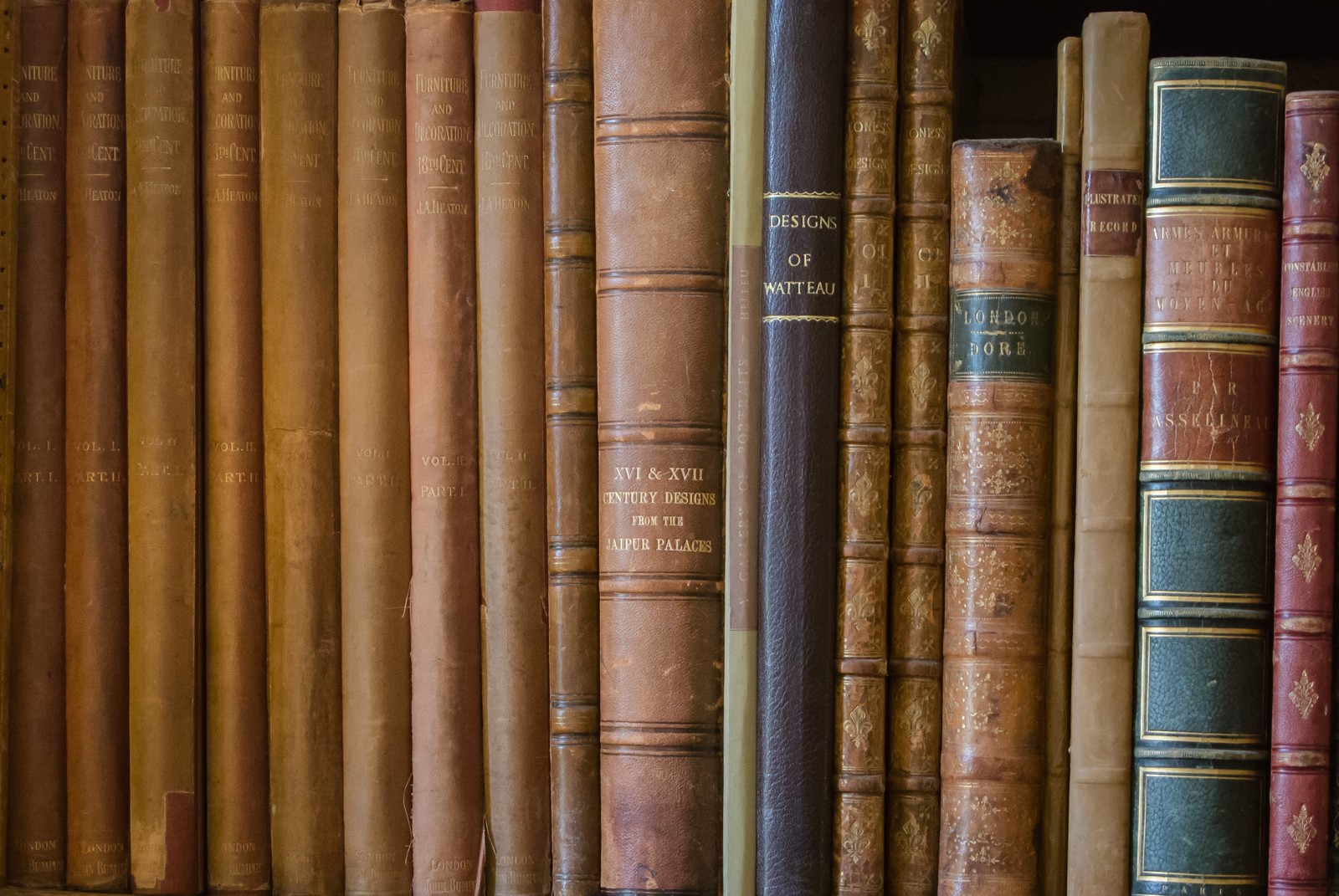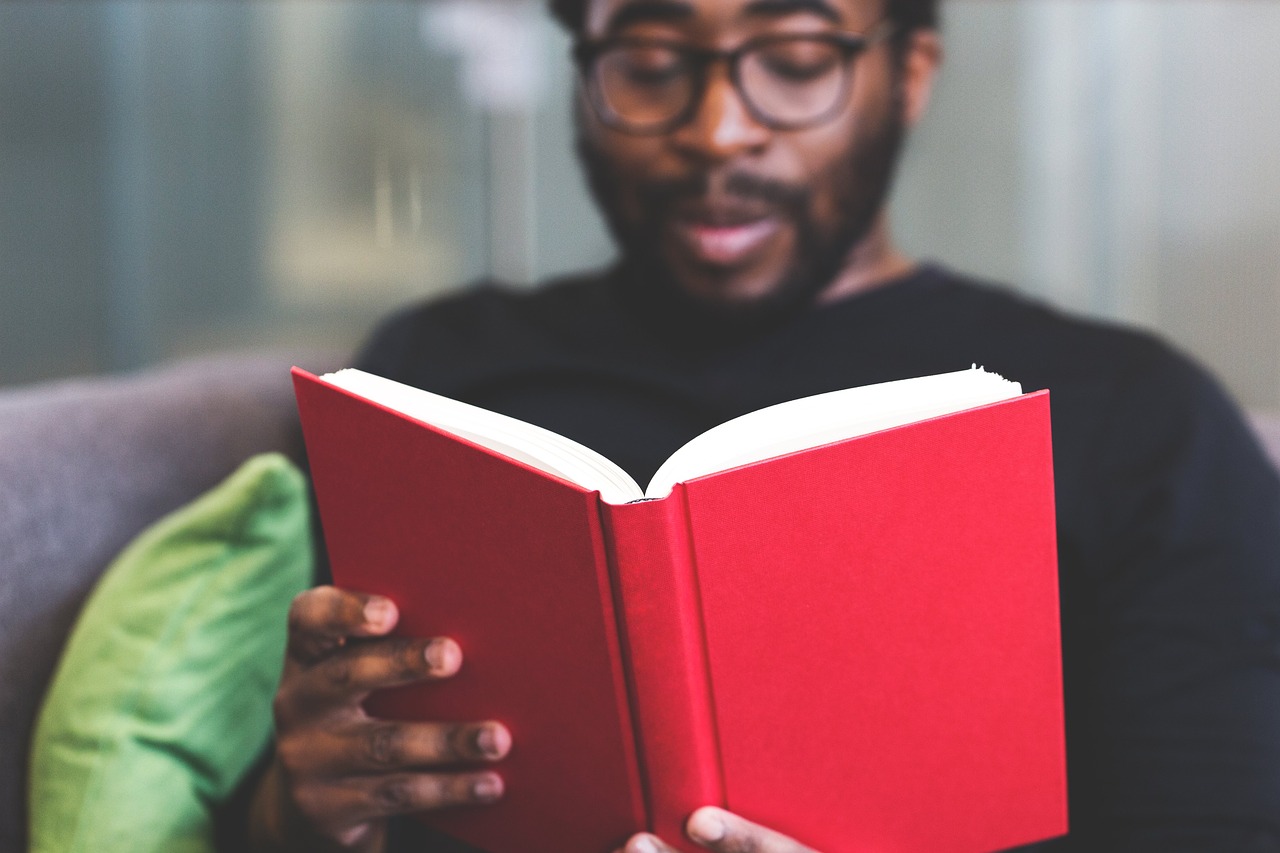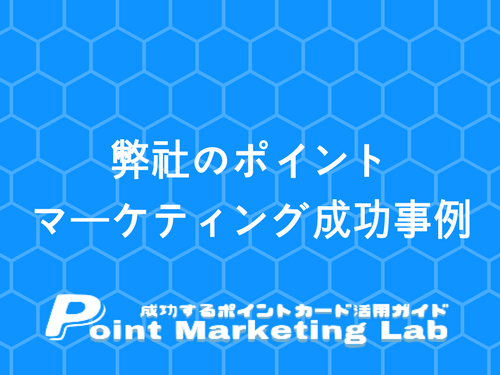目次
エムズコミュニケイト 佐藤 信二
最新記事 by エムズコミュニケイト 佐藤 信二 (全て見る)
- 会員組織の立ち上げの効果を考える - 2017年8月29日
- マーケティングでは顧客情報の活用が重要です。 - 2017年8月1日
- 【専門家監修】ロイヤルカスタマーを重視すべき理由 - 2017年8月1日
こんにちは。CRM/ポイントサービスコンサルティングのエムズコミュニケイト(2018年4月に大日本印刷グループよりMBO致しました)が運営するポイントマーケティングラボ編集部です。
こちらのサイト、ポイントマーケティングラボでは、企業・事業会社のマーケティング・販売促進の担当者・事業責任者の方々に向けて、ポイント制度の導入やCRMのノウハウについて、プロの視点から惜しみなく情報を発信して参ります。
是非ご参考にしていただければ幸いです。
それでは、以下から本題です。
「カスタマーリテンション」という言葉は聞いたことはあるでしょうか?
CRMの担当者やマーケティングの担当をされている方なら、耳にしたことのある言葉かもしれません。今回は、この「カスタマーリテンション」について掘り下げて考えてみたいと思います。
「カスタマーリテンション」いわゆる顧客リテンションとは、顧客を維持することを意味します。
近年、どんなものでも多くの選択肢から自由に選べる世の中になっています。だからこそ、消費者は様々なブランドをまたいで利用するようになっていると思います。
反面、企業側からするとそのような「ジプシー」のような顧客の心をどうやって掴めば良いか難しい点だと思います。
そもそもカスタマーリテンションの必要性や重要性は何なのでしょうか?
今回は、カスタマーリテンションの重要性と顧客維持を成功させる方法について、お話してみたいと思います。
カスタマーリテンションとは?

「カスタマーリテンション」の言葉の意味自体、そこまで世の中に浸透しきっていないかもしれません。
「カスタマーリテンション」とは、顧客を繋ぎとめ、継続的に売上を伸ばすために必要な『顧客維持』を意味します。
『顧客維持』というのは、
- 現在の顧客に引き続き商品やサービスを使い続けてもらう
- 今以上に商品を頻繁に購入してもらう(サービスを利用してもらう)
- より高額な商品の購入
以上の目的を果たすためにおこなう施策のことです。
これらの達成のためには、短絡的でその場しのぎの対策ではなく、顧客との強固な関係性を育てる必要があるといえます。
カスタマーリテンションの重要性

顧客維持の必要性について、もう一度おさらいしてみましょう。
ある大きなバケツがあったとします。大きなバケツに水をいっぱいにするために、いかに効率良く水を入れるかを考えているとします。
しかし、勢いよく水が入っているにも関わらず、バケツにはなかなかいっぱいになりません。
よく見たら、底に穴が空いていました。
そうです、既に入っている水(既存顧客)がどんどん流出していってしまえば、いくら新しい水(新規顧客)を入れてもバケツの水の量は増えません。
また、いずれ水資源は尽き(市場の飽和)、新規顧客獲得も難しくなってくるのです。
そうなると、今の顧客をこれ以上減らさないよう、企業のファンを作ることや逃げてしまった顧客を再度捕まえることが考えられます。
しかし、既に逃げた客は何らかのマイナス要素を持って逃げた場合も大いに考えられます。
となると、いかに今の顧客に対してアプローチをしていくのが、得策でしょう。
一般的に、『パレートの法則』と呼ばれる原理では、大体売り上げの80%は20%のヘビーユーザー、すなわち優良顧客によって生み出されていると言われています。
カスタマーリテンションの重要性についてもう少し掘り下げて考えてみます。
自社の商品を一度購入してもらいそれきりになってしまった顧客に、再度自社商品を購入してもらう方法はあるのでしょうか?
よほど顧客が欲しいと思う動機がある場合、または企業側から何かしらのアプローチする、この二つのどちらかになるでしょう。
他社との競争は激化し、競合他社が力をつけて魅力的な商品が提示されれば、自社の既存顧客もサービスの乗り換えを検討する可能性は十分にありえます。
また、該当するような競合がいなくとも、顧客が商品やサービスに対し何かしらの大きな不満を抱えてしまえば、利用を停止したり商品のリピート購入はなくなるでしょう。
現在でいえば、競合他社が存在しないビジネスは、すでにほとんど存在しないのではないでしょうか。大体の業界では、複数の競合他社がひしめき合っていて、各社顧客の取り合い合戦が繰り広げられていることだろうという状況でしょう。
つまり、全くその商品や業界について知らない新規顧客を開拓するというのは現実問題なく、どちらかというと、顧客が「あの会社、この会社」とコロコロ変えていっているという状況もありえます。
なので、顧客に一度選んでもらえば万事安泰というわけではないのです。
選んでもらってからが勝負ともいえるかもしれません。他社の商品ではなく、ウチの「この商品を使いたい」と思ってもらえる工夫が必要です。
自社の商品・サービスに愛着を持ってもらえるような努力、それと同時に顧客との関係構築が大事なのです。
「顧客で居続けてもらうこと」いわゆるカスタマーリテンションがどれほど大事なのかお分かり頂けたでしょうか?
カスタマーリテンションの重要性に気付いていない場合も?

しかし、やはり中にはカスタマーリテンションの重要性に気付いていない場合もあります。もしくは、重要性に気付いてはいるが、売り上げの低下の原因がそれだと思っていないパターンです。
例えば、「売上が下がってきている。このままではいけないので、何か解決策を考えなければ」ということで、「○○をリニューアルしたい」という結論になったとします。○○というのは、Webサイトの再設計や、新聞広告やカタログのリニューアルなどです。
しかし、よく考えてみてほしいのです。「リニューアル」でそれは根本解決するのでしょうか?
新規顧客獲得にものすごく力を入れているのに、売上の低下や伸び率が鈍化してはいないでしょうか?
新規商材の紹介や季節に応じた商品リコメンド、商材のセレクトだってきちんとされており、クリエイティブにも工夫をしている・・・・なのになぜ顧客は徐々に離脱している、こんなに良いものを毎月届けているのに、なんで売上が伸びないのだろう?という悩みをかかえているのではないでしょうか?
カスタマーリテンションが上手くいかない、なにが問題?

問題は2つあります。
問題点①
1つ目は何よりも、顧客の状況に応じたリテンション施策がとられていないという点です。
例えば、定期的に配布するパンフレットや無料冊子などは全員に同じものを届けていることでしょう。
しかし顧客の側に立てば、そのブランドや企業との関係が長い顧客もいれば、まだまだ日が浅い顧客もいますよね?また、顧客歴が長いといっても、いつも同じ商品だけ買う人もいるし、はたまた幅広く商品を買ってくれる人もいるでしょう。
ブランドや企業の商品を購入し始めたころと現在とでは顧客の興味・関心や悩みも変わっているかもしれません。
それにもかかわらず、全員に何も考えなしに同じ施策を展開していて良いのでしょうか?
問題点②
2つ目の問題は、新規顧客の獲得の指標が「獲得の量と効率」を主軸としている点です。
獲得の量や効率を目的とすることは、アクイジション(新規顧客獲得)では当然です。しかし、リテンションを行うような段階では「質」も同時に指標として見ていく必要もあります。
実は、「質」の評価はすぐには結果がでないため、新規顧客獲得時のように数値を短期的に確認するものではなく、中期的に観察していかなくてはいけません。
つまり何が言いたいかというと、獲得の「量と効率」にばかり目が行き「質」に対しての優先順位が下がったがために、そのつけが数年後に売上低下となって現れることがあるということです。
カスタマーリテンション以外に関するマーケティング施策に関してもご紹介しています。
本記事とともに参考にしていただける内容ですので、下記リンクよりぜひご覧ください‼
カスタマーリテンションを成功させる方法は?
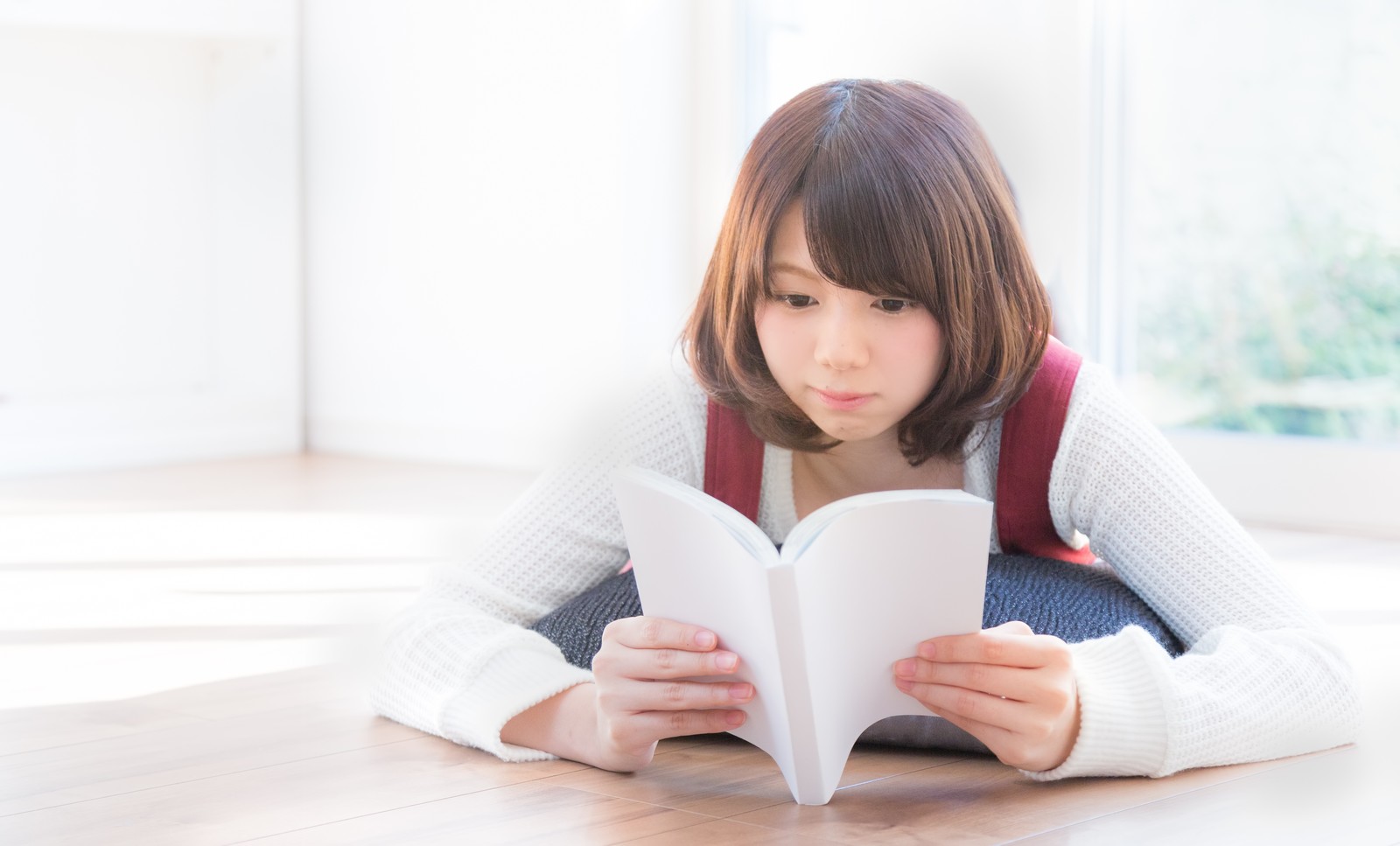
上記の問題はどのように解決していったら良いのでしょうか?
やはり、もっと既存顧客の維持・活性化の施策に注力することに行き着きます。
既存顧客の中でも、得意客(優良顧客)のニーズをヒアリング・吸い上げ、適切なタイミングで商品や付随品(サービス)を提案しましょう。
それによって、取引数の増加ならびにブランドスイッチ(顧客の離反)を防ぐ効果が期待されます。また、リテンション施策を続けていく中で、顧客ニーズを満たす製品・サービスが自社のものとマッチしなくなってくる場合もあるかもしれません。
その場合は、新商品開発のチャンスです。
時代は流れ、流行は移り変わります。柔軟に対応できる企業は長く生き残ることができます。そのためには、顧客の声に耳を傾けることが必要なのです。
つまり、リテンションは非常に重要な戦略であり、企業の栄枯盛衰の生命線と言っても過言ではないのです。
カスタマーリテンションをマーケティングで成功させる

マーケティングにおいては、顧客維持よりも新規顧客獲得のほうに注目が集まることが多いように感じます。
しかし、前述の通り安定して売上成果を上げるためには、新規顧客の獲得と同じく、いえそれ以上にカスタマーリテンションにも注力していきたいところなのです。
それでは、どのようにしたらマーケティングに活かせ、売上や顧客満足度などが高まっていくのかを考えてみましょう。
施策その1:「顧客の声に耳を傾けた対応をする」
当然ともいえますが、顧客からの要望・クレームをしっかりと聞き、柔軟な対応を見せていくことが顧客との信頼関係につながります。
商品に対するクレームというのは、顧客はもちろん不満を持っています。しかし同時に「商品・サービス、そして企業に対して強く期待している」とも言えるのです。
わざわざ電話をかけたりメールを書いたりする労力をかけても、どうにかしたいという期待があるということです。反対に、そもそもその期待すらない人はクレームすら言わず去っていきます。
だからこそ、クレームこそがチャンスになってくるのです。
クレームを通した期待にしっかりと応える、さらには期待以上の対応を見せることができれば、自社のファンになってくれるチャンスに変えられるのです。
また、そういった顧客の声に耳を傾けるために、窓口を広げるというのも施策のひとつです。
たとえば、「無印良品」を展開している株式会社良品計画では、公式の問い合わせ窓口だけでなく、ソーシャルメディアを活用した顧客とのつながりを大事にしています。
気軽に顧客がフィードバックできる場所で、企業がより多く顧客の声を取り入れることができます。社員のモチベーションアップにつながる効果もあるようです。
こういった双方向でつながるソーシャルメディア対応も顧客との関係を築く上で重要な役割を担っているでしょう。
施策その2:「他社のサービスにはない明確なメリットを提供し続ける」
自社の商品・サービスが、現状では競合よりも売上が上がっているとしても、油断は禁物です。この状態を保つことは難しく、決して気は抜けません。
今は自社が他社をサービス面で上回ったとしても、時間が経過すれば競合他社も進化します。
おごることなく、常に競合について、顧客に自社の商品サービスを使い続けてもらうために必要な事柄についてを学び、対策していかなければなりません。
明確なメリットの一つとして、パーソナライズされたOne to One施策も他社との差別化になるでしょう。業態や扱う商品にもよりますが、より個別対応していくことで、顧客に「いい思い」を味わってもらい満足度の向上を図ります。
たとえば、全国ホテル等の運営を行っている株式会社星野リゾートでは、リピート顧客のデータを非常に細かくチェックし、分析をおこなっています。
たとえば、顧客の「部屋のCDを増やして欲しい」といった要望なども個別に検討し精査しているそうです。年に何回かいくうちの家族旅行などで、より多く星野リゾートを利用してもらえるように工夫をおこなっているようです。それこそが安定集客を可能にする仕組みとなる、と考えているのでしょう。
施策その3:「優良顧客になることのメリットを演出する」
2つめの施策にも言えることですが、顧客は「いい思い」をしたいものです。
自分だけが特別扱いを受ければ悪い気はしません。そういった心理を上手く使うのもカスタマーリテンション施策の一つです。
継続して利用することによって得られる特典や、よりきめ細やかなサービスが受けられるようになるなどのメリットを提案しましょう。顧客のニーズに合う内容であれば、競合への乗り換えを思いとどまる要素のひとつになる可能性も高いでしょう。
どういったサービスや特典が適当かは、顧客のデータをじっくり分析したり、顧客の声に耳を傾けることで分かってきます。
顧客にとって、自分の利用状況や好みを把握し、自分に合わせてサービスを提供してくれることは大変特別な価値になります。
もちろん、純粋に「良いサービスの提供」は顧客にとって重要です。
しかし、それ以上に「自分だけの対応」は満足度が高いです。
「個々への対応による関係性」は顧客とのつながりをより強め、商品やサービスへの愛着を育てていくことが可能です。
こういった個々に応じた細やかな対応という「メリット」の提供についても、尽力していけるのが、重要な施策の一つといえるでしょう。
絶対に重視したいカスタマーリテンションのまとめ
カスタマーリテンションは重要と言われ続けている昨今、それに気付いていない企業もいるかもしれないということから今回は言及してみました。激しい競争社会の中で企業が生き残って顧客に選ばれ続けるのは、避けては通れない道だということが分かって頂けると幸いです。
※カスタマーリテンションや顧客維持の重要性についてさらに詳しく!こちらも合わせてお読みください
ポイントサービス導入をご検討の会社様は、弊社エムズコミュニケイトにご相談ください!
①国内唯一・取り組み実績(エムズコミュニケイト)
国内で唯一のポイントサービスに特化したマーケティングコンサル会社です。これまでのポイントサービスの導入・改善支援は300社以上あり、通販、小売り、サービス、金融、鉄道・航空、ガス電力など幅広い業界において実績があります。
※ポイントサービス導入改善に関する国内初の指南書を出版
②サービス設計からシステム導入・運用までワンストップ支援
顧客課題を解決するサービス設計からシステム導入・運用まで、ポイントサービスにまつわる業務全般をワンストップでご支援することが可能です。ポイントサービス戦略設計、システム構築、個人情報管理、運用支援、プロモーション、カード発行、コールセンター、ポイント交換商品の発送管理など上流~運用までを網羅的にサポート可能です。
③ポイントサービス運用に関する法的・会計面のサポート
ポイントサービスの運用に必要な法的(景品表示法)、会計面(2021年から上場企業に強制適用されるポイント会計)において十全なノウハウを保有しサポートします。
※ポイント会計についてはEY新日本監査法人への執筆協力で『ポイント制度のしくみと会計・税務』(中央経済社)を出版。
④中立性を加味したシステムベンダー紹介
ポイントサービスのコンサルティング支援にあたり、ポイントシステムベンダーについては、中立性を重要視しております。貴社のニーズにあったベンダー紹介および、システムのカスタマイズ提案が可能です。