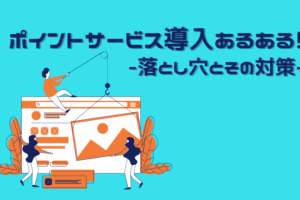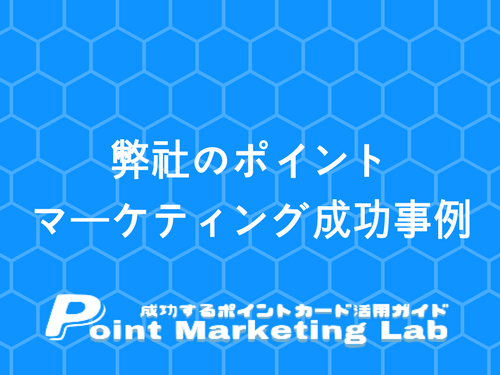目次
エムズコミュニケイト岡田 祐子
最新記事 by エムズコミュニケイト岡田 祐子 (全て見る)
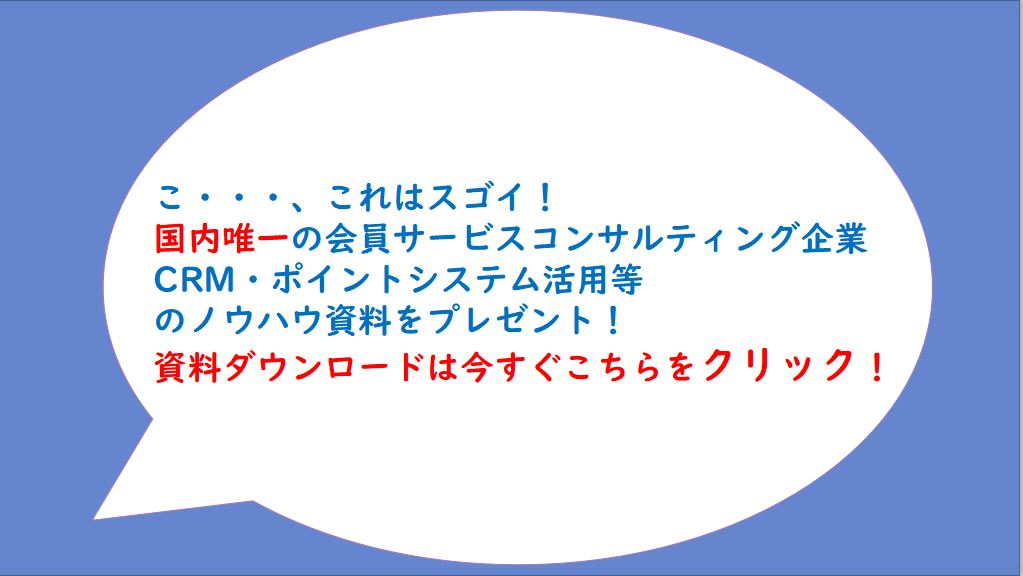
こんにちは。CRM/ポイントサービスコンサルティングのエムズコミュニケイト(2018年4月に大日本印刷グループよりMBO致しました)が運営するポイントマーケティングラボ編集部です。
こちらのサイト、ポイントマーケティングラボでは、企業・事業会社のマーケティング・販売促進の担当者・事業責任者の方々に向けて、ポイント制度の導入やCRMのノウハウについて、プロの視点から惜しみなく情報を発信して参ります。
是非ご参考にしていただければ幸いです。
それでは、以下から本題です。
ポイントには大きく分けて2種類あるのをご存知でしょうか?色々な場面で使える「共通ポイント」と、自社だけで使える「自社ポイント」があります。
この「共通ポイント」と「自社ポイント」にはどのような違いがあるのでしょうか?詳しく見ていきましょう。
共通ポイントの仕組みって?

TポイントやPontaポイントなど、今やどのお店に行っても見かけないことがないと言えるのが共通ポイント。ご存知の方も多いかと思いますが、その仕組みについて改めておさらいしてみましょう。
また、企業側の運営方法や狙いなども考えていきたいと思います。
共通ポイントは、その名の通り、複数の店舗をまたいで、またある時には業種を問わず、あらゆる店舗で同じポイントが貯めることのできる便利なポイントの仕組みです。消費者側からすれば、色々な店舗でポイントを貯めることが出来るので、貯めやすく貯まりやすく、利便性が高く感じることが多いでしょう。
また、同時に多くの共通ポイントでは、1ポイントを1円として、仮想通貨の役割を果たし、お得にお買い物が可能になります。
そういった、貯まりやすさと使いやすさを実現したのが、共通ポイントの仕組みとも言えるでしょう。
共通ポイントのメリット

ポイントカードには色々とメリットがありますが、利用する機会がないポイントを貯めても意味はありません。その点、共通ポイントは色々な場面で利用できるので便利です。
共通ポイントの特徴は、繰り返しになってしまいますが個別の業種に限らず様々な業種にまたいで使用できることです。共通ポイントの代表例で言えば、Tポイントやポンタですが、これらはコンビニ、レンタルショップ、ファミレスなど多岐に渡ります。
活用範囲が大きい
共通ポイントは多くの場合、100円の買い物につき1ポイントが付与され、1ポイント=1円で使用できます。
これらのポイントは実生活でも利用範囲が広いため便利なのですが、インターネット上でも利用可能なため、その活用範囲はさらに大きくなります。
相互送客
ある店舗で買い物をすると、レシートに別の店舗のクーポンが付いてくることがあります。これにより、別の店舗に消費者を誘導することができます。
ポイントはこれまで「顧客の囲い込み」としてのツールとして使われてきましたが、それに加え「顧客の誘致・誘導」のツールとして、共通ポイントは利用されています。囲い込みは囲い込みでも、これまでとは規模の違う「加盟店同士での囲い込み」を行おう、ということです。
大手共通ポイントに参加すれば、知名度も上がり、また相互送客の効果により、新規顧客の獲得にもつながるメリットがあります。
ブランディング効果
今日、共通ポイントとして知られているのはいずれも、大きな経済圏を築いてきています。
消費者にも広く認知されているので、その経済圏に加盟することによって、加盟企業はイメージアップや信用度アップなどの効果も狙うことができるでしょう。
現在共通ポイントに加盟している企業数は、日々増えております。たとえば消費者目線考えた時に「ここTポイント使えるんだ!」と思わせたならばユーザーにとってはプラスに作用するでしょう。
顧客に見捨てられにくい
こちらも一種のブランディング効果と言ってしまえば、そうかもしれませんが、共通ポイントは顧客に見捨てられにくいでしょう。
理由としては、財布の邪魔となるポイントカードがこれ以上増えることもないですし、顧客の利用率の高いポイント経済圏に入ることが出来れば、「ついで」でもポイント利用を促すことが出来るからです。見捨てられないというのは、企業の販促や集客にとって重要な要素です。
共通ポイントのデメリット
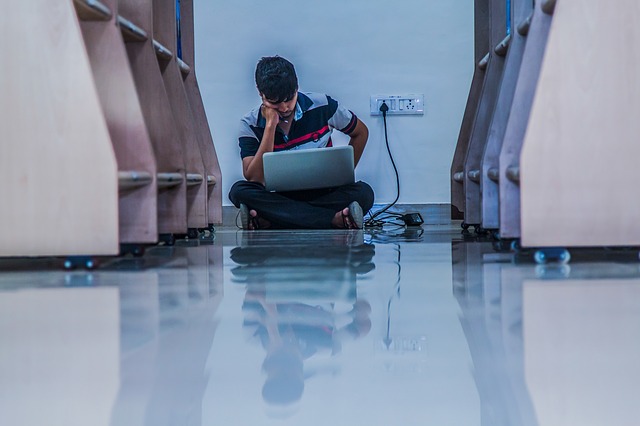
良いことづくめの共通ポイントに見えますが、デメリットも勿論あります。
独自性を出しにくい
発行元の仕様に依存するため、自社の独自性を発揮しにくいというデメリットがあります。
また、「同じポイントがもらえる」ということであれば、加盟店であれば「どの店舗でもポイントがもらえる」ということになります。どこの店舗であってもポイントを貯めることができるため、差別化が難しくなってきます。
顧客情報の利用
これは一見するとメリットと捉えられそうなものです。しかし、顧客情報は加盟店が自由に利用できるものではなく、あくまで運営会社によって管理され、公表されないことが多いです。Tポイントの場合、加盟店向けに「Tカードを利用になったT会員の所在地・利用ポイントの状況・リピート率・購入単価の4つを月単位でお知らせします」との記載があります。利用できる情報は限定的なのです。
ポイントを運営する会社には、カードを利用した消費者の様々な情報(行動・購買履歴など)が集まります。加盟店はそういった情報を一部利用させてもらっている、というイメージが近いと思います。つまりは、購入の回数が低い企業が闇雲に共通ポイントに参加したからと言って必ずしも、ポイントカードの恩恵を受けれるわけではない事を認識する必要があります。
では共通ポイントのデメリットや陥りやすいものを改善するには何をやれば良いのでしょうか?それはしっかりと、社内で自由にどのような顧客なのかを分析出来る環境を整えることが重要です。
大手共通ポイントを比較

さて、皆さんも良く知る共通ポイントはいくつか存在していますが、その特徴について、簡単にまとめていきたいと思います。
楽天ポイント
言わずと知れた、楽天ポイントですが、楽天ポイントは楽天市場を大きな経済圏として使われることを想定される共通ポイントです。ネット通販では、あらゆる店舗が楽天市場に加盟しており、何かインターネット上で買い物する上で、避けては通れない経済圏と言っても決して間違っては居ません。
しかし、その楽天経済圏はネットだけに留まらないのが近年の状況です。コンビニではサンクスと提携し、飲食店ではミスタードーナツなどと提携しています。また、他共通ポイントの領域でも楽天ポイントが貯められるように、来店するだけで貯められる「楽天チェック」など、オフライン上での進出が顕著と言えるでしょう。
Pontaポイント
Pontaポイントは、ローソンのイメージが強いという人も多いでしょうか。それは間違ってはいません。そのほかには、DVDレンタルやゲームで知られているゲオなども加盟店としては有名でしょう。
楽天ポイントと比べると、ネットというよりもリアルに特化したポイントに見られがちですが、2015年にリクルートと提携開始したことが、ネット上でも使う場面が増えてきました。リクルートが運営している、ホットペッパーやじゃらんなどの人気サービスで、Pontaポイントが利用できるようになったことは非常に大きいでしょう。
今まで課題とされてきた、ポイント利用場面の増加が、さらなるPontaポイントの発展に期待が持てます。
Tポイント(新Vポイント)
Tポイントを知らない人はいないくらい、絶大な認知があるのは、決して過大評価ではありません。共通ポイントのはじまりは、Tポイントであり、それゆえ世間での認知度も圧倒的です。もともと、レンタルビデオ店だったTSUTAYAで使えるTポイントがはじまりです。そのTポイントが業界をまたぎ、あらゆる店舗で使えるようになりました。
コンビニではファミリーマート、飲食店ではガストなど、今や加盟店舗は2016年9月時点でも56万店舗にも上っています。Tポイントカードを持っている会員数は、6000万人いるようです。とはいえ会員数は、Pontaポイントや楽天ポイントの会員数より劣っていますが、加盟店舗数は圧倒的で、約50万店舗です。
また、Yahooポイントとも2013年以降提携をはじめ、リアルだけでなくネットに対してもその手を伸ばしつつあります。
楽天ポイントは、もともとネットに強みを持っていて、そこからリアルへと拡充していっていますが、Tポイントは逆です。リアルでの展開からのネットへの進出といえるでしょう。
(2024年4月22日以降、TポイントはVポイントと統合し『Vポイント』として利用できます。)
詳しく解説した記事は以下のリンクから参照いただけます。
dポイント
ドコモユーザーには馴染み深いdポイントですが、これは共通ポイントとしては一番新入りといったところでしょうか。以前は、ドコモポイントとして運営されていましたが、加盟店数が少なく、使いどころに困っている会員が多いと言われていました。
2015年以降dポイントとして生まれ変わり、共通ポイント業界に参入していきましたが、まだまだ提携企業数としては1万程度、他の共通ポイント群には見劣りします。
ただ、今後提携企業は大きく拡大していくことは予想され、またPontaポイントと相互交換できるところも、ユーザー側からの「使い道」という観点では、不足感はそこまでないでしょう。
自社ポイントのメリット

独自性を発揮
共通ポイントのデメリットの裏返しになりますが、自社で運営するポイントであるため、自由度は当然高くなり、より自社の実情にあったものを作り出しやすくなります。場合によっては、独自性を発揮し、他社との差別化にも成功するかもしれません。
顧客情報の利用
これも共通ポイントのデメリットの裏返しになりますが、自社で運営しているポイントであれば、そこから得た顧客のすべての情報を知ることができます。そこからさらにキメの細かいサービスを展開していくことも可能です。
より詳細な情報から、質の高い顧客の囲い込みを行うことや、より高度なマーケティングにより、他社との差別化を図ることも可能になります。
自社ポイントのデメリット

導入・運用負担
当然、自社で運用するわけですから、導入にかかる費用、運用していくにあたっての負担は全て自社にかかってきます。その負担を軽減しようと簡素なポイントシステムを導入すると、より高度な顧客情報も得られないただの「値引き」ポイントとなってしまうこともあり得ます。
既存顧客の囲い込み
既存顧客をきちんと囲い込めるのであれば、ポイントのもともとの目的・役割は全うできたと言えるでしょう。しかし、導入や運用を続けていくための負担をケチって、システム整備が不十分なポイントを導入してしまった場合、他社のポイントにはつけ入るスキがたくさんありすぎます。また、雑なシステムで顧客のイメージが低下し、他社に乗り換えられるということもあるかもしれません。
これでは、「顧客の囲い込み」という本来の役割は果たせそうにもありませんね。
また、自社でのみのポイントですので、システムがきちんと構築され、商品の質も文句なしであれば、既存顧客の囲い込みには効果的ですが、新規顧客の獲得には至りません。

〈まとめ〜共通ポイントと自社ポイントの相違点〉
総合的に見れば、独自性は出しにくいものの、共通ポイントのメリットは大きいように思います。商品開発による新規顧客の獲得だけではない、別の新規顧客獲得の機会が持てるのですから。
ただ、ネームバリューがすでにあり、その業界で高いシェアを誇り、ケチることなく自社ポイント運営にかかるコストを負担できるのであれば、自社ポイントも効果的だと思います。
「共通ポイント」「独自ポイント」両者どちらもメリット・デメリットが勿論あります。
それを踏まえた上で特にポイントサービスを導入することの、前提として考えて頂きたいのは、ポイントサービスは、ただの値引きのツールではなく、顧客を区別することが重要であることを認識してください。
顧客として獲得し、常連顧客として根付いてくれれば、情報も取得できその顧客が何を望んでいるのかが、見えてくると思います。
ポイントサービス導入をご検討の会社様は、弊社エムズコミュニケイトにご相談ください!
①国内唯一・取り組み実績(エムズコミュニケイト)
国内で唯一のポイントサービスに特化したマーケティングコンサル会社です。これまでのポイントサービスの導入・改善支援は300社以上あり、通販、小売り、サービス、金融、鉄道・航空、ガス電力など幅広い業界において実績があります。
※ポイントサービス導入改善に関する国内初の指南書を出版
②サービス設計からシステム導入・運用までワンストップ支援
顧客課題を解決するサービス設計からシステム導入・運用まで、ポイントサービスにまつわる業務全般をワンストップでご支援することが可能です。ポイントサービス戦略設計、システム構築、個人情報管理、運用支援、プロモーション、カード発行、コールセンター、ポイント交換商品の発送管理など上流~運用までを網羅的にサポート可能です。
③ポイントサービス運用に関する法的・会計面のサポート
ポイントサービスの運用に必要な法的(景品表示法)、会計面(2021年から上場企業に強制適用されるポイント会計)において十全なノウハウを保有しサポートします。
※ポイント会計についてはEY新日本監査法人への執筆協力で『ポイント制度のしくみと会計・税務』(中央経済社)を出版。
④中立性を加味したシステムベンダー紹介
ポイントサービスのコンサルティング支援にあたり、ポイントシステムベンダーについては、中立性を重要視しております。貴社のニーズにあったベンダー紹介および、システムのカスタマイズ提案が可能です。