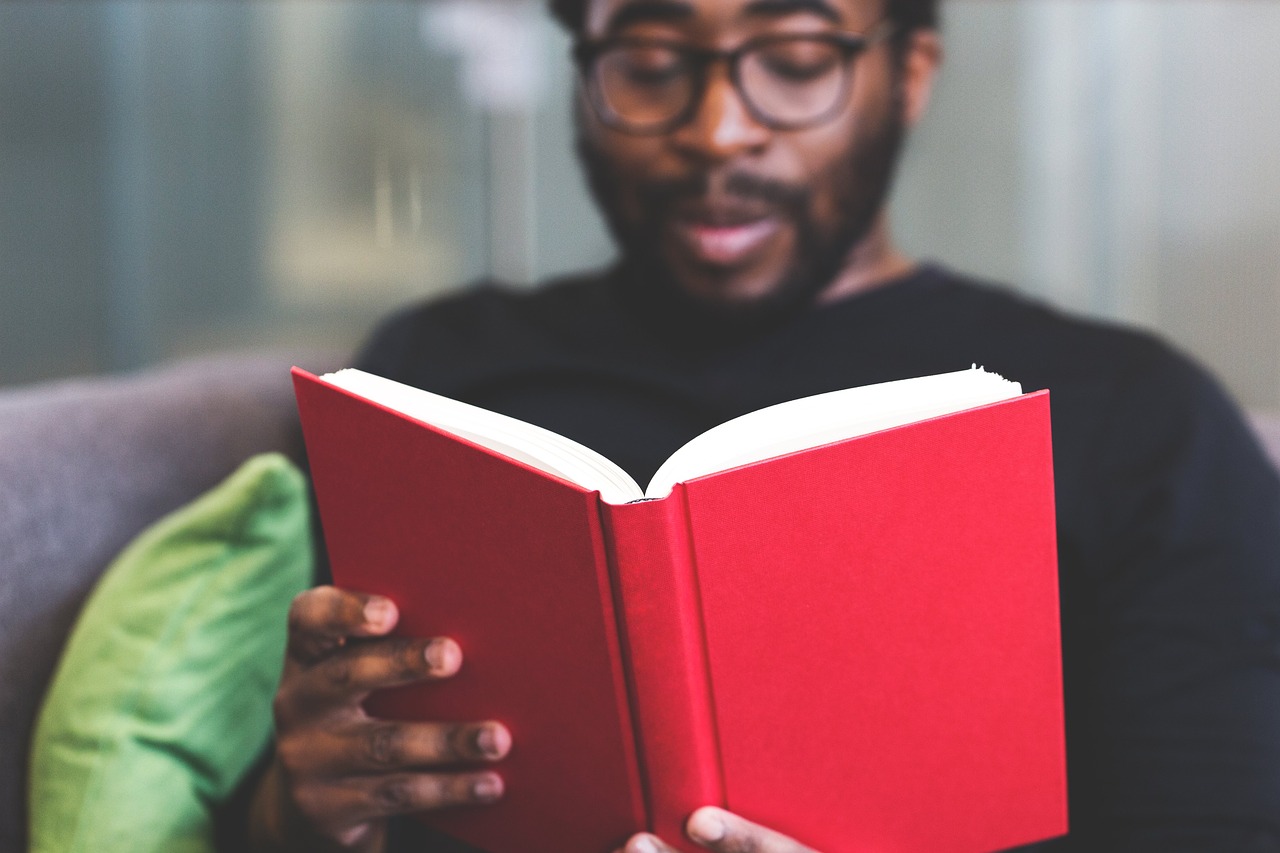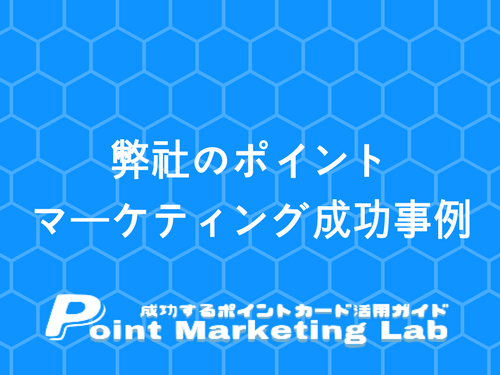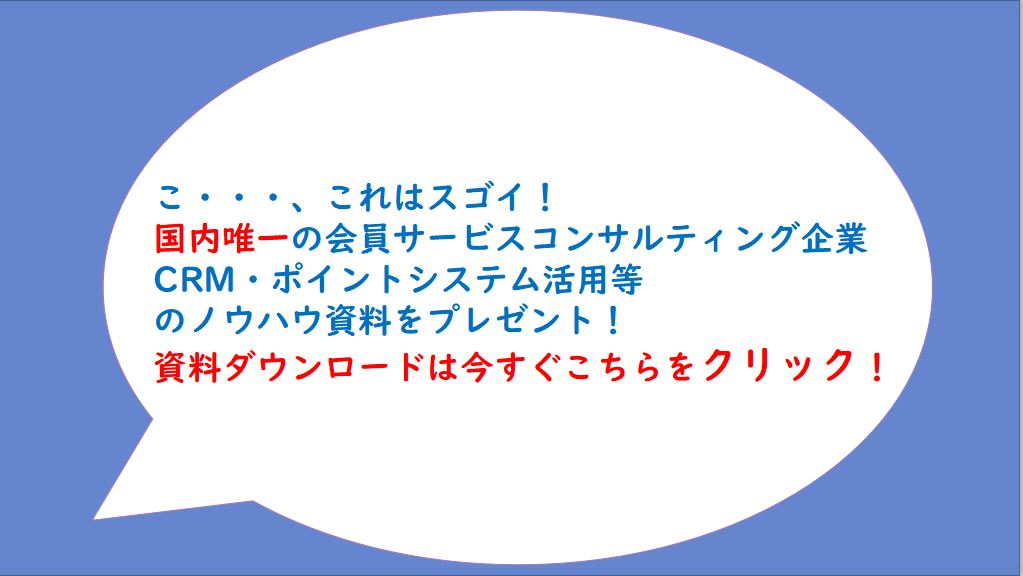目次
エムズコミュニケイト 佐藤 信二
最新記事 by エムズコミュニケイト 佐藤 信二 (全て見る)
- 会員組織の立ち上げの効果を考える - 2017年8月29日
- マーケティングでは顧客情報の活用が重要です。 - 2017年8月1日
- プロ目線から考えるロイヤルカスタマーを重視すべき理由 - 2017年8月1日
こんにちは。CRM/ポイントサービスコンサルティングのエムズコミュニケイト(2018年4月に大日本印刷グループよりMBO致しました)が運営するポイントマーケティングラボ編集部です。
こちらのサイト、ポイントマーケティングラボでは、企業・事業会社のマーケティング・販売促進の担当者・事業責任者の方々に向けて、ポイント制度の導入やCRMのノウハウについて、プロの視点から惜しみなく情報を発信して参ります。
是非ご参考にしていただければ幸いです。
近頃のマーケティング手法として重要視されている「ユニファイドコマース(Unified Commerce)」をご存じですか?
今回は、顧客へのより最適なアプローチをしたい!という方々に向けた解説と成功事例をまとめました!!
ユニファイドコマースとは?O2O・オムニチャネルの違いは?
近年、消費者の行動が多様化し、あらゆるデバイスで情報を得ることができるようになりました。
それに伴い、マーケティング手法も順応していかなくてはいけません。
そして、現代重要視されているのが「ユニファイドコマース」です。
従来注目されていたO2Oマーケティングやオムニチャンネルという言葉はご存じでしょうか?
これらについて簡単に違いを説明すると、
- ユニファイドコマース:顧客一人一人に併せた価値のある購入体験を提供
- O2Oマーケティング:顧客のパターンに併せた購入までの顧客誘導
- オムニチャンネル:様々な媒体を用いて顧客にアプローチする囲い込み手法
ユニファイドコマースとは?
ユニファイドコマース(Unified Commerce)とは、
「オンライン・オフラインを問わないあらゆるチャネルの顧客データを統合することで、一人一人の顧客に取って最適なサービスを提供するというマーケティング手法」です。
ECサイトや実店舗で取得したデータ(顧客情報・行動履歴など)を統合することで、顧客一人一人にあったアプローチを可能にしています。これが顧客満足度につながり、顧客の囲い込みや離反防止にもつながっていくという考えです。
例えば、実店舗で購入した商品の情報がアプリ上でもみることができ、さらにアプリでは1つの店舗情報に限らないグループ会社等の情報を一括でみることができるのもユニファイドコマースを取り入れた事例です。グループ会社も含めた情報共有を行うことで、顧客にとっても企業にとっても便利なスタイルが構築出来るのです。
O2Oマーケティングとは?
Online to Offline Marketingの略が、「O2Oマーケティング」のことを指しています。具体的な意味は、集客手法のことです。
ここでポイントなのは、①「オンライン to オフライン」だけではなく②「オフライン to オンライン」の意味も含んでいるということです。
O2Oの意味:その①「オンラインtoオフライン」
これはWeb上で集客し、それをリアル店舗に誘導し、購買をしてもらうというマーケティング施策のことです。
以前の広告手法では、当該商品やブランド認知を広めることで集客していましたが、近年はその集客方法に限界が生まれてきました。
消費者は必要な情報しか手に入れないようになり、従来の「広告」は流し見され、消費者に全く刺さらなくなっているのです。すなわち、企業側からすると集客効果が薄いものになってきたのです。
そこで、より特定の消費者層にターゲティングして広告を出す手法にどんどん変わってきています。より効果が上がりやすい消費者にWeb広告を提示し、具体的なメリットを認知してもらうのです。
O2Oの意味 その②「オフラインtoオンライン」
②の「オフライン to オンライン」というのはどのような手法でしょうか?これには、最近の消費者の購買行動が背景にあります。
インターネットで必要な情報が簡単に・的確に見れるがゆえに、リアル店舗に足を運んでも、その場で「買わない消費者」が増えてきました。店舗に実際に商品を手に取る→実物を確認→ネットで口コミや価格などを調査→一番低価格なショップ(オフライン、オンラインにかかわらず)で購入。これが「買わない消費者」の買い物の仕方です。
つまり、「オフライン to オンライン」というのはその消費者行動の流れにのっとり、『オンライン』の購入の時点で巻き取ろうとする手法です。他社のECサイトで購入させるのではなく、自社のオンラインサイトで購入してもらうメリットを訴求するという手法です。
効率的な収益化のために見込み顧客を取り逃さないようにすることは重要です。そのためにチャネルを横断するマーケティング手法が重要となり、O2Oマーケティングが普及しました。
オムニチャンネルとは?
「O2Oマーケティング」というのは、集客の手法であり、顧客を誘導させる施策です。
それに対して、「オムニチャネル」というのは、顧客の誘導はしません。これは、囲い込みの手法です。前述通り、消費者はあらゆるデバイスや多様なチャネルを通じて、自分に必要な情報を導き出しています。ゆえに、企業側も一つのチャネルだけで訴求していくだけでは、顧客を取り逃がしてしまう可能性が高くなります。
見込み顧客が関わるであろうチャネルに施策を打ち、消費者との接点を複数持つということです。
例えば、実店舗メインのアパレルメーカーが近年ECサイトにも力を入れてきているのは、その大きな特徴ともいえるでしょう。
今までは、店舗での購入をメインとしていましたが、これからは店舗に来なくても、オンラインでも購入できる、もしくは両方で購入できるように、会員情報を統合したりして利便性を上げているのも、オムニチャネルの施策を一つです。
ユニファイドコマースを取り入れた成功事例

【アパレルブランド】ユナイテッドアローズ
実店舗メインでおこなっていたアパレルブランドのユナイテッドアローズは、早くからオム二チャネルやO2Oマーケティングに力を入れていました。
同社では、ECサイトでも店舗でも商品が購入できるようになっており、会員情報も統合されています。ECサイトから実店舗の誘導ならびに、店舗来店してくれた顧客に有効な来店促進のアプローチも可能です。
なんといっても、ユナイテッドアローズのアプリやECサイトは、店舗誘導の効果を持ったものといえます。Web上で、店舗ごとの在庫を表示することで、顧客が欲しい商品の情報を店舗に行かなくても手に入れることが出来ます。
まさにオンラインオフラインに関係なく、顧客の望むスタイルで自由な買い物を可能にしている事例といえます。
さらに、近年はポイント施策に力を入れており、「UAクラブ会員サービス」に登録すると、より一層お得に買い物ができる特典やランク制が用意されています。
https://store.united-arrows.co.jp/guide/members/
【小売業】ルミネ
駅の近くですぐに買い物ができる便利さと若者に人気なお店を多くそろえているルミネも、ユニファイドコマースをうまく活用している事例の一つです。
日本中に展開しているルミネだからこそ、ショップ情報等を一つ一つ集めるのは大変です。そこで登場したのが「One LUMINE」というアプリです。ルミネやニューマンのショップ情報やイベント情報をゲットでき、お気に入り登録や購入をすればマイルも貯まります!マイルを使えばお得に買い物もできます!
事業規模が大きいからこそ行えるユニファイドコマースの成功事例と言えるでしょう。
https://www.lumine.ne.jp/onelumine/
【メガネ】JINS
メガネショップで有名のJINS(ジーンズ)も、ユニファイドコマースの成功事例です。
メガネの度数が分からなかったり前回いいと思ったメガネがどれかわからない、保証書をなくしてしまって修理の際に困るなど、様々なお悩みがメガネユーザー共通であると思います。そんなお悩みと企業側のマーケティング手法を合体させたのがこの事例です。JINSアプリがあれば、保証書・度数データ・クーポンを持ち歩くことができ、さらにはオンラインショップでバーチャル試着まで出来てしまいます。
準備をしたうえでお店で買うしか選択肢がないと思っていたメガネ市場に新しい風を吹かせた事例といえるでしょう。
https://www.jins.com/jp/jinsapp/
まとめ
インターネットを活用したマーケティングから進化し、現代に求められるのは網羅的で利便性の高いマーケット作りだということがお分かりいただけたでしょうか。
O2Oマーケティングやオムニチャンネルから発展したユニファイドコマースという新しいマーケティング手法を取り入れることで、より一層顧客に寄り添った手法が増えていくといえるでしょう。
アプリを使った集客方法や様々な企業が行っている戦略の事例についてコチラでも解説しております。是非ご参考ください。
ポイントサービス導入をご検討の会社様は、弊社エムズコミュニケイトにご相談ください!
①国内唯一・取り組み実績(エムズコミュニケイト)
国内で唯一のポイントサービスに特化したマーケティングコンサル会社です。これまでのポイントサービスの導入・改善支援は300社以上あり、通販、小売り、サービス、金融、鉄道・航空、ガス電力など幅広い業界において実績があります。
※ポイントサービス導入改善に関する国内初の指南書を出版
②サービス設計からシステム導入・運用までワンストップ支援
顧客課題を解決するサービス設計からシステム導入・運用まで、ポイントサービスにまつわる業務全般をワンストップでご支援することが可能です。ポイントサービス戦略設計、システム構築、個人情報管理、運用支援、プロモーション、カード発行、コールセンター、ポイント交換商品の発送管理など上流~運用までを網羅的にサポート可能です。
③ポイントサービス運用に関する法的・会計面のサポート
ポイントサービスの運用に必要な法的(景品表示法)、会計面(2021年から上場企業に強制適用されるポイント会計)において十全なノウハウを保有しサポートします。
※ポイント会計についてはEY新日本監査法人への執筆協力で『ポイント制度のしくみと会計・税務』(中央経済社)を出版。
④中立性を加味したシステムベンダー紹介
ポイントサービスのコンサルティング支援にあたり、ポイントシステムベンダーについては、中立性を重要視しております。貴社のニーズにあったベンダー紹介および、システムのカスタマイズ提案が可能です。