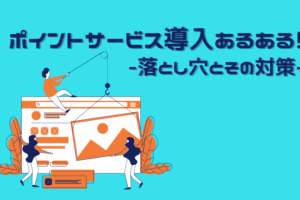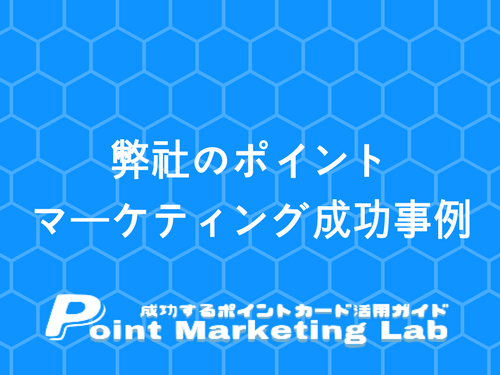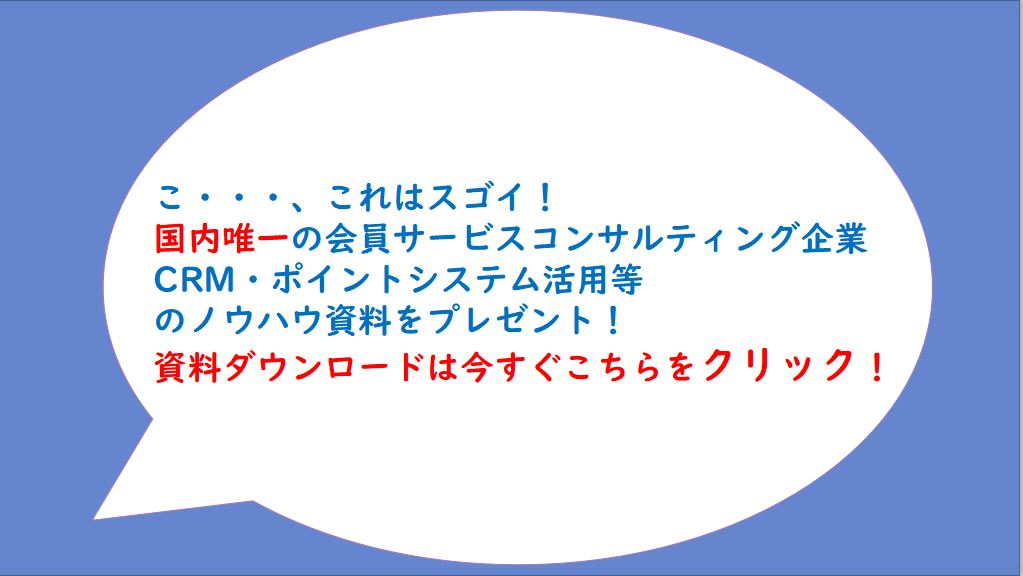エムズコミュニケイト岡田 祐子
最新記事 by エムズコミュニケイト岡田 祐子 (全て見る)
PayPayが2022年10月より共通ポイント市場に参入することが発表されています。現時点での共通ポイント業界は、dポイント、Ponta(ポンタ)、Tポイント、楽天ポイントの4社ですが、PayPayの参入に伴い、共通ポイント事業者はこの大手5社が競争状態となります。
この記事では、
- PayPay共通ポイント参入の経緯
- PayPayポイントの解放概要
- PayPayとキャッシュレス決済の現状
- PayPayポイントその他の特徴
- 今後の展望
についてまとめ、PayPayの共通ポイント参入にまつわる情報をお伝えしていきます!
PayPay共通ポイント参入の経緯
PayPayは2020年度において共通ポイント各社と比較し、PayPayボーナスだけで2位ぐらいの金額を発行しており、ポイントを他社に開放することによって、2023年には業界1位の発行額となる共通ポイントに成長させたい考えがあります。(1位の楽天ポイントは2020年で4,700億ポイントを発行、累計では5兆ポイント以上を付与していますが、2022年下期には逆転の射程圏内に入ることを見通しています。)
PayPayポイントの解放概要
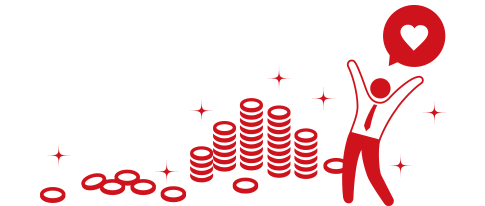
- PayPayでの決済利用など、ソフトバンクグループ内での利用に対するインセンティブとしてPayPayポイントを付与しますが、10月以降はこれをグループ外へと開放。希望すれば企業はポイントをPayPayから購入し、それを自社の利用客に対して、決済金額に応じて付与することを可能としています。
- 100万ポイントまで10%のPayPayポイントを還元するというキャンペーンを実施した場合、飲食店がPayPayから100万ポイント分を購入して付与する店舗独自のキャンペーンを実施できます。(従来なら、PayPayがキャンペーンを実施しない限り、PayPayによるボーナス還元を提供できませんでした。)
- PayPay決済を導入していない企業でも、支払額に応じてPayPayポイントを貯めることができます。
PayPayとキャッシュレス決済の現状
- 利用者数が累計で4,700万人を超え、決済取扱高は4兆円超。PayPayクーポン利用者も、2022年3月時点で1,000万人を突破しています。「決済動向2022年4月調査」(インフキュリオン社調べ)によると、QRコード決済アプリの利用率でPayPayは「楽天ペイ」や「d払い」などを抑えて1位となっています。
- コンビニエンスストアはNewDaysに対応したことでほぼ制覇し、さらには全47都道府県の自動車税、1,129自治体の市税などの支払いにも対応したことで利用範囲も広がりました。
- 日本のキャッシュレス比率の伸び率は7年間で平均2%、2010年から2015年で5%しか上がっていませんでしたが、ここ5年は11.5%増と急拡大。このままの勢いで行けば、政府目標の「2025年にキャッシュレス比率40%」は、1年前倒しとなる2024年に実現できる、との予測が立てられています。
PayPayポイントその他の特徴
- PayPay銀行やPayPay証券、PayPayカードや保険などとの連携でユーザーの囲い込みを図っています。
- 「貯める」・「支払う(使う)」に加え「運用する」ことも可能なのも特徴です。

(https://paypay.ne.jp/guide/point/より)
今後の展望
加盟店開拓という視点で、PayPayがライバルとの違いを出すための鍵を握るのが、ユニクロを傘下に持つファーストリテイリングや家電量販最大手のヤマダホールディングスといった共通ポイントを採用していない企業の獲得と言われています。またPayPayの共通ポイント参入はキャンペーン参加のみなど、自由度があるため、従来の「共通ポイント加盟店」といった概念を覆す展開も見込まれています。
参考記事)日本経済新聞電子版(有料会員限定版)「PayPay参入、共通ポイント業界の勢力図はどう変わる」
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC197HT0Z10C22A7000000/
以下の記事ではTポイントからの企業の離脱についてまとめています。本記事と併せ、ポイント市場の動向を知るにお役立てください!
ポイントサービス導入をご検討の会社様は、弊社エムズコミュニケイトにご相談ください!
①国内唯一・取り組み実績(エムズコミュニケイト)
国内で唯一のポイントサービスに特化したマーケティングコンサル会社です。これまでのポイントサービスの導入・改善支援は300社以上あり、通販、小売り、サービス、金融、鉄道・航空、ガス電力など幅広い業界において実績があります。
※ポイントサービス導入改善に関する国内初の指南書を出版
②サービス設計からシステム導入・運用までワンストップ支援
顧客課題を解決するサービス設計からシステム導入・運用まで、ポイントサービスにまつわる業務全般をワンストップでご支援することが可能です。ポイントサービス戦略設計、システム構築、個人情報管理、運用支援、プロモーション、カード発行、コールセンター、ポイント交換商品の発送管理など上流~運用までを網羅的にサポート可能です。
③ポイントサービス運用に関する法的・会計面のサポート
ポイントサービスの運用に必要な法的(景品表示法)、会計面(2021年から上場企業に強制適用されるポイント会計)において十全なノウハウを保有しサポートします。
※ポイント会計についてはEY新日本監査法人への執筆協力で『ポイント制度のしくみと会計・税務』(中央経済社)を出版。
④中立性を加味したシステムベンダー紹介
ポイントサービスのコンサルティング支援にあたり、ポイントシステムベンダーについては、中立性を重要視しております。貴社のニーズにあったベンダー紹介および、システムのカスタマイズ提案が可能です。