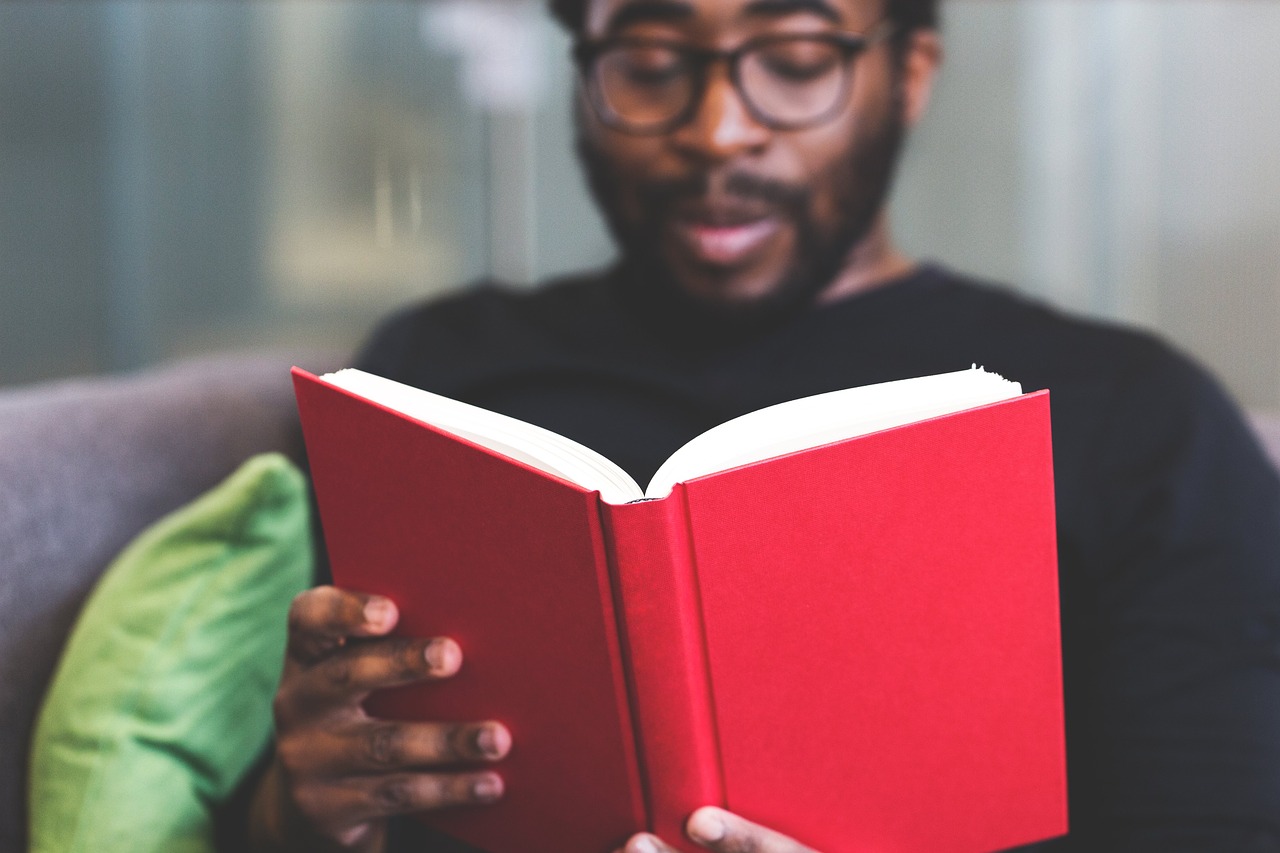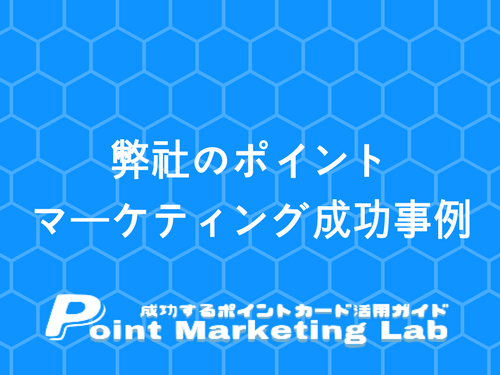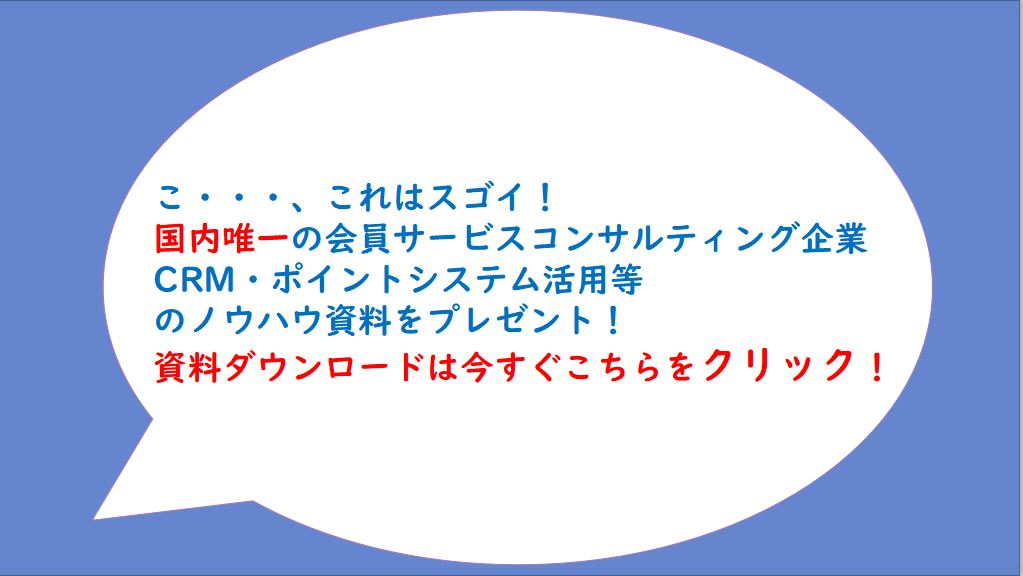目次
エムズコミュニケイト 佐藤 信二
最新記事 by エムズコミュニケイト 佐藤 信二 (全て見る)
- 会員組織の立ち上げの効果を考える - 2017年8月29日
- マーケティングでは顧客情報の活用が重要です。 - 2017年8月1日
- プロ目線から考えるロイヤルカスタマーを重視すべき理由 - 2017年8月1日
こんにちは。CRM/ポイントサービスコンサルティングのエムズコミュニケイト(2018年4月に大日本印刷グループよりMBO致しました)が運営するポイントマーケティングラボ編集部です。
こちらのサイト、ポイントマーケティングラボでは、企業・事業会社のマーケティング・販売促進の担当者・事業責任者の方々に向けて、ポイント制度の導入やCRMのノウハウについて、プロの視点から惜しみなく情報を発信して参ります。
是非ご参考にしていただければ幸いです。
顧客に満足して頂けているのか…、顧客の求めているものは何か…など、どんな企業にも顧客にまつわる悩みが多くあるのではないでしょうか。
更には、ナーチャリングや顧客育成、CRMなどの言葉をよく耳にするものの、何が有効なのかわからないという方も多くいるのではないでしょうか。
そこで、今回は「ナーチャリング」という言葉の説明から、顧客育成がどうして重要なのか、どうすれば「優良顧客」を生み出せるのか、などについて詳しく解説していきます!!
ナーチャリングとは?
何もしなくても顧客自身が「優良顧客」になってくれれば、企業にとって願ったりかなったりです。しかし、現実はそう甘くありません。すなわち、企業は自分たちにとって優良な顧客を「意図的に」増やす必要性があるのです。
それがいわゆる「顧客育成」と呼ばれるものです。顧客の育成というのは、「ナーチャリング」という言い方も使われています。
「ナーチャリング」とは、直訳すると「育成」という意味で、ビジネス用語として「顧客育成」を指します。
実は顧客育成というのは、以下の2つの段階を総合して使われる言葉です。
- 見込顧客が情報収集の段階から購買に至るまでの期間に行われるアプローチ
- 購買されてから、リピートに至るまでの期間に行われるアプローチ
今回は、顧客維持というところにフォーカスをしてお話ししていきたいので、2の「購買されてから、リピートに至るまでの期間に行われるアプローチ」について掘り下げていきたいと思います。
顧客育成を行う際に抑えておきたいこと

では、顧客維持・育成がなぜこんなにも大切と言われているのでしょうか?
「長期利用をしてくれる顧客がいないのであれば、代わりに新規顧客を取って来ればいいだけの話ではないのか?」と思う人もいるかもしれません。
それでも顧客育成が重要な理由の裏には、実は大きなポイントがあるんです!!
すでに顧客になっていた人に更なる満足感を感じて貰う事で、複数回の購入だけに限らない、より大きな利益が生まれるといわれています。
そこで、既存顧客を育成、ならびに維持するのが大事な理由についていくつか挙げたいと思います。
新規顧客の獲得が大変な理由3選!!
近年さらに、新規顧客獲得は困難な時代と言われています。それはなぜでしょうか?
新規顧客獲得までには、多くのプロセスがあるからです。このプロセスを経て、ようやく新規の顧客になってくれます。
- 市場・潜在顧客へのアプローチ
自社製品について全く興味を抱いていない層にアプローチするためには、展示会や広告などの集客プロモーションを使うことが多いようです。
しかし、この層にこういったアプローチをしても、すぐに顧客になってくれるわけではなく、成功しても「見込顧客」になるという最初のステップを踏み出したに過ぎないのです。 - 見込顧客へのフォロー
①をふまえて欠かせないステップが次の「見込顧客へのフォロー」です。これは、その企業の商材が高額であればあるほど重要になります。まだ顧客ではありませんが、ここでいかにコミュニケーション構築を図り、より確度の高い見込顧客にしていくかが重要です。
一般的にインターネットプロモーション(ホームページやメルマガなど)は、見込顧客を有望見込顧客にするという側面において効果を発揮すると言われています。 - 有望見込顧客への落とし込み
単なる見込顧客だったところから次のステップに進むと、ニーズが顕在化してくる有望な見込顧客になります。
この段階に進んではじめて、個々のニーズに沿った売り込みができるようになります。
どのような商品や企業形態であっても、これらのプロセスを経て新規顧客が獲得されて行くので、多少の時間と労力をかける必要があるといえます。
しかしながら、悲しいことに離反していく顧客が一定数いるというのも事実です。だからこそ、離反顧客を上回る新規顧客獲得を狙うだけではなく、既存顧客や見込み顧客を進化させていく事が重要なのです。
顧客育成・既存顧客維持にかかる「コスト」
直前に、労力が非常に掛かるということは挙げたばかりですが、コストの面でも既存顧客維持コストの方がリーズナブルといえるかもしれません。
新規顧客を獲得するコストは、既存顧客を維持するコストに比べると少なくても5倍、人によっては10倍にもなるという説があります。コスト面からみても、それだけ新規獲得が大変なのです。
だからと言って、既存顧客の維持がラクかといったら、決してそうではありません。きちんと既存顧客のニーズに向き合わなければ継続してもらうことは難しいですし、良好な関係性を築くことはできません。
顧客育成のメリット:顧客を知る良い機会になる
既存顧客を育成すること、ならびに既存顧客を維持するためのアプローチは、顧客を知る良い機会になるといわれています。
これは、自社の商品がどういった顧客にニーズがあるのか、顧客の求めるものが本当は企業が思っているものが違っているのではないか、そういったことを確かめるチャンスになるからです。
これは、商品開発や商品改善にも役に立つでしょう。顧客を良く知り、親和性が増せば、顧客が顧客を呼ぶこと、いわゆる「バズり」さえも可能にするのです!!!
そして結局、顧客に向き合うことは結果的に良いことが多いと言えます!

既存顧客の育成方法
では、既存顧客の育成にはどのような手段があるのでしょうか?
一度商品を購入してくれた顧客や、サービスを利用してくれた顧客に対して重要な点は「いかに早めにアプローチするか」ということが重要になってきます。
会員ポイントサービス(カード)を用いたアプローチ
一度サービスを利用してもらった顧客がポイントカードを作っていたり、会員になってくれたならば、そこからアプローチするのが最も良いでしょう。ポイントカードの登録時には、会員情報として顧客情報を得ることができるため、その情報を活用して様々なアプローチをすることが可能です。
とはいえ、初回顧客の場合だと注意も必要です。
しつこいアプローチはかえって嫌われてしまう可能性があるので、頻繁なアプローチは良くありません。それを踏まえて、いくつか手法を挙げてみます。
1.再来店促進のDM等を送る
商品・サービスへの興味関心は購入時点が最も高いと言われています。そして、それは次第に下がっていく傾向が顕著です。そこで、購入した商品やその企業(ブランド)のことを記憶に残してもらうために有効な手段の一つがDMと言われています。
そして再来店してもらうには、強い動機付けが必要になります。そこで有効なのが、特別な割引クーポンを付ける等、次回のお得さや次回購入を想像できるきっかけを作る事です。また、その場限りのリピートではその後の顧客育成として意味がないので、商品理解を深めるコンテンツを入れるのも効果的です。
顧客がどうしたら商品・サービスへの期待値を持続させてくれるのか、顧客目線でアプローチする事が重要なのです。
2.ポイントカードのポイント還元率に変化をもたせる
ポイントの還元率に変化をもたせるのは、既存顧客育成には有効な手段ともいえます。
例えば、特定の期間のみ還元率を大幅UPさせる方法です。これを来店してもらうきっかけにするということです。
また、会員のランクごとに変化を持たせるのは、中長期的な顧客の来店モチベーションの一つになるかもしれません。例えば、初回客:1%、ライト顧客:2%、優良顧客予備群:3%、優良顧客:5%などの差別化も、手法の一つです。
そのほかのアプローチ
新規購入者に、試供品やサンプルなどを配布し、一人の顧客に対して他の商品をアプローチする方法も有効です。実際にある程度の期待感をもって、自社の商品を購入してくれたはずなので、その顧客層に合うサンプル品は、響く可能性が高いのです。
その際重要なのが、商品・サービスに対する正しい理解を促進させることでしょう。特に、化粧品など使用感が重要な商品やサービスなどは、購入した商品を正しく使用していないと効果が現れにくく、不満につながることが多いようです。正しい使用方法を理解させるコミュニケーションを図ることが、今後購入に至ったときに、期待値とのギャップ感がなくなり、企業イメージも良くなります。
このような、商品の価値を実感させるアプローチは、顧客育成の可能性を広げるだけでなく、そういった工夫をしているという企業へのイメージUPさせることにつながるでしょう。
優良顧客の育成

既存顧客を育成する方法をご紹介してきました。それでは次に優良顧客として育成していく手法を考えてみます。
普通の顧客と優良顧客との差はなんでしょうか?
一度でも自社の商品を購入してくれた顧客は、当然「大切なお客様」であることは変わりありません。しかし、「頻度も高く、長い期間、リピートしてくれたお客様」はもっともっと大事です。
そういった「ファン」と呼ばれる顧客を出来る限り作る工夫というのは、企業にとって利益になると同時にイメージUPに繋がります。
利益になるのは、当然、リピート率が上がり一人当たりの購入単価が高くなり、その人数が増えれば売上は増加します。ではなぜ、企業の印象が上がるのでしょうか?
それは、『ファンが増える=顧客満足度が高い』ことを意味しているからです。顧客からその「商品・サービスに満足した!」と思ってもらえればもらえるほど、良い商品であり、良い対応をしてくれるという印象が相対的に高まります。そうなると、そういった印象は、次第に広まっていき、顧客が顧客を呼ぶ状態になるからなのです。
ではそういった状態に少しでも近づけるためには、どういった施策が必要なのでしょうか?
優良顧客を増やすための施策
1.顧客ニーズを整理し、明確化する
優良顧客になってもらうには、現在の顧客が何を求めているのか正確に把握する必要があります。
顧客は段階ごとに、欲しい情報や知りたいことが違ってきます。
例えば、まだ商品購入に至ってない人であれば、「試供品やサンプルはあるのか?」「比較検討できるカタログ等はあるのか?」など商品価格が高いものであればあるほど、商品自体の情報が欲しくなるでしょう。その一方で、すでに購入してくれた顧客であれば、「カスタマイズはできるのか」「会員サービス(特別待遇)などはあるのか?」「メンテナンスについて知りたい」などそのもの自体を良くしたり、特別扱いしてほしいなどの願望も出てきます。
こういった異なったニーズをきちんと把握することがまずは重要です。求めていないことを企業がおこなっても、『押し売り感』が出てしまったり、企業としての誠意が伝わらない可能性もあるので、今後のファンという観点においては厳しいものになってしまいます。
2.「顧客」を「個客」として接する(もてなす)
ニーズが分かれば、そのニーズをどう具現化するかというところになるでしょう。一度商品を購入した顧客は特に、特別扱いされたいという願望を必ず持っています。なので、ひとりひとりに対して、より親身に接することが重要です。
3.顧客の行動を元にした、カスタマー対応
例えば、とあるECサイトで定期購入している商品があるとします。いつもその商品のオプションを少し変更して購入しているのですが、それを今回はうっかり忘れてしまったとします。その際に、顧客に対して「普段されている購入手法を取られていないけど、お間違いないですか?一旦キャンセルして変更後の再購入も可能です」と一言確認を入れるとどうでしょうか?
その顧客が実際に間違って購入手続きをしてしまっていても、そうでなくても好印象なのではないかと思います。なぜかというと、「その顧客の購入状況を把握して、フォローしてくれている」からです。また、「まだ変更可能」と本来なら出来ないはずのことを「出来る」としてくれる特別感も良いでしょう。
その他、顧客が「こんなものが欲しい!」「こんなイベントがしたい!」という声を組んで、会員限定のイベントに招待するのも、特別感や優越感が得られる体験になるでしょう。
顧客育成は顧客のライフタイムバリュー向上とも密接に関係します。以下の記事も併せてご一読いただくことで、さらにお役に立てれば幸いです!ぜひご覧ください。
ライフタイムバリュー(LTV)の最大化で顧客との関係性を改善!マーケティング手法やアプローチ方法を専門家が細かく解説!!
CRMに有効な方法:DX

ここまでの話を踏まえて、どのような顧客に対しても有効な手段として挙げられるのが「DX化」を進めることです。
近年よく聞く「DX」ですが、まず初めにこの意味を確認しましょう。
DXとは?
DXとは、生活を豊かにするためにデジタル技術を活用することを指します。
ビジネスにおいては、デジタルを活用することでシステムの導入だけではない、顧客価の創出や、組織文化のリセット、従業員の業務売りつかなどを促進し、最終的には収益構造の変革や収益の増加を狙って行われます。
即ち、少し前から言われている「IT化」が指す「デジタル導入」に留まらない、企業という組織全体の効率性を挙げるデジタル改革という事が出来るでしょう。
DXとCRMの関係性は?
では、このDXが企業の顧客育成にもたらす影響は何でしょうか?なぜ有効な手段といえるのでしょうか?
顧客育成の方法には顧客理解やCRM(顧客との関係構築)を進める必要があります。具体的に必要となる方法はここまでに明記して来ましたが、それらを一括で解決する方法がDXといえるのです。
1人1人の顧客にあったアプローチをすることは、紙媒体での管理等従来のやり方では追い付かないのが現実です。
反対に、デジタル導入をすれば会員登録されている顧客情報を一括で管理でき、同系統の顧客に対してまとめてアプローチをすることも簡単になります。
具体的な例を挙げると、会員登録の際に誕生日を入力してもらった場合、同じ誕生月の人全員に一斉に「誕生日割引クーポン」を配布することが出来ます。
また、ポイントサービスを導入・運用する際にも便利です。
ポイントの貯まり具合によって見込み顧客~優良顧客のどこに位置しているのかを判断できます。見込顧客に対して誕生日クーポンを配布することで再来店を促す等、顧客の状況に合わせたアプローチも可能です。
これらの事から、DX化を進めることは企業にとっても顧客にとっても有効な手段なのです。
まとめ〜ビジネスで使われる「ナーチャリング」とは?優良顧客の育成やCRMにはDXが有効!?
顧客を育成していくのは、BtoC、BtoBいずれのビジネスでも難しい部分は多いでしょう。
しかし、顧客ひとりひとりとの良好な関係構築は、いま築こうとしているファンだけでなく、その先にあるファンから影響を受けた潜在顧客にまで届く可能性も大いにあります。「ファンがファンを呼ぶ」と言えば大げさかもしれませんが、顧客満足度の高い商品は次第に広まっていきます。そういった仕掛け作りは非常に有用であり、継続的にフォローしていくべきであると、今回はご紹介させていただきました。
また、こちらの記事では顧客の囲い込みについて詳しく触れています。是非ご覧ください。
ポイントサービス導入をご検討の会社様は、弊社エムズコミュニケイトにご相談ください!
①国内唯一・取り組み実績(エムズコミュニケイト)
国内で唯一のポイントサービスに特化したマーケティングコンサル会社です。これまでのポイントサービスの導入・改善支援は300社以上あり、通販、小売り、サービス、金融、鉄道・航空、ガス電力など幅広い業界において実績があります。
※ポイントサービス導入改善に関する国内初の指南書を出版
②サービス設計からシステム導入・運用までワンストップ支援
顧客課題を解決するサービス設計からシステム導入・運用まで、ポイントサービスにまつわる業務全般をワンストップでご支援することが可能です。ポイントサービス戦略設計、システム構築、個人情報管理、運用支援、プロモーション、カード発行、コールセンター、ポイント交換商品の発送管理など上流~運用までを網羅的にサポート可能です。
③ポイントサービス運用に関する法的・会計面のサポート
ポイントサービスの運用に必要な法的(景品表示法)、会計面(2021年から上場企業に強制適用されるポイント会計)において十全なノウハウを保有しサポートします。
※ポイント会計についてはEY新日本監査法人への執筆協力で『ポイント制度のしくみと会計・税務』(中央経済社)を出版。
④中立性を加味したシステムベンダー紹介
ポイントサービスのコンサルティング支援にあたり、ポイントシステムベンダーについては、中立性を重要視しております。貴社のニーズにあったベンダー紹介および、システムのカスタマイズ提案が可能です。