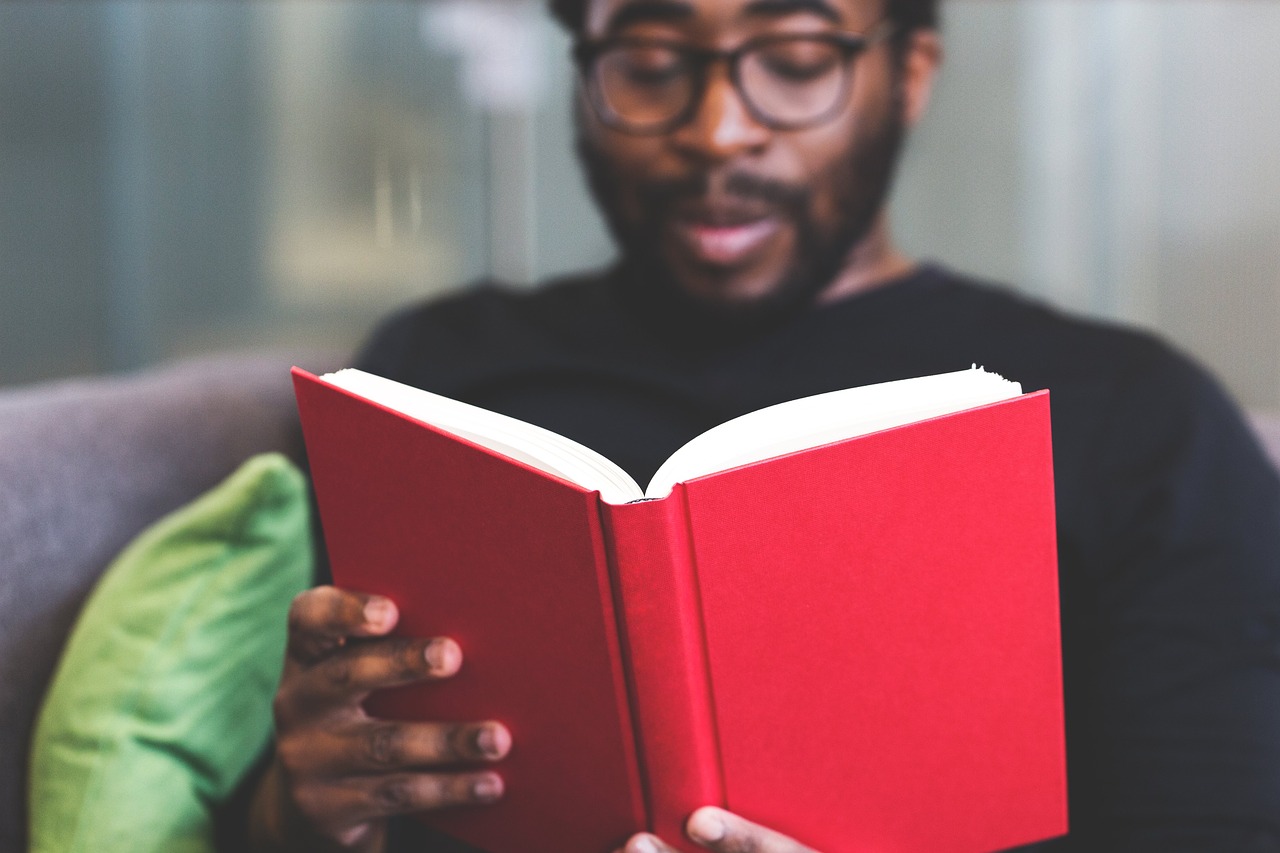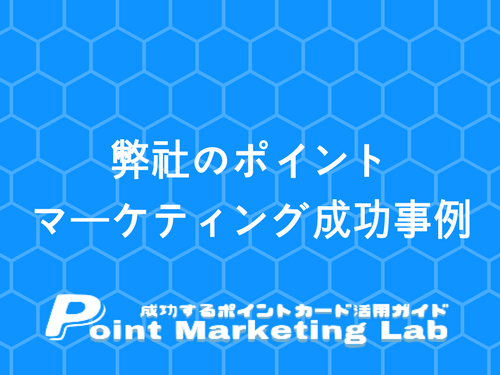目次
エムズコミュニケイト 佐藤 信二
最新記事 by エムズコミュニケイト 佐藤 信二 (全て見る)
- 会員組織の立ち上げの効果を考える - 2017年8月29日
- マーケティングでは顧客情報の活用が重要です。 - 2017年8月1日
- プロ目線から考えるロイヤルカスタマーを重視すべき理由 - 2017年8月1日
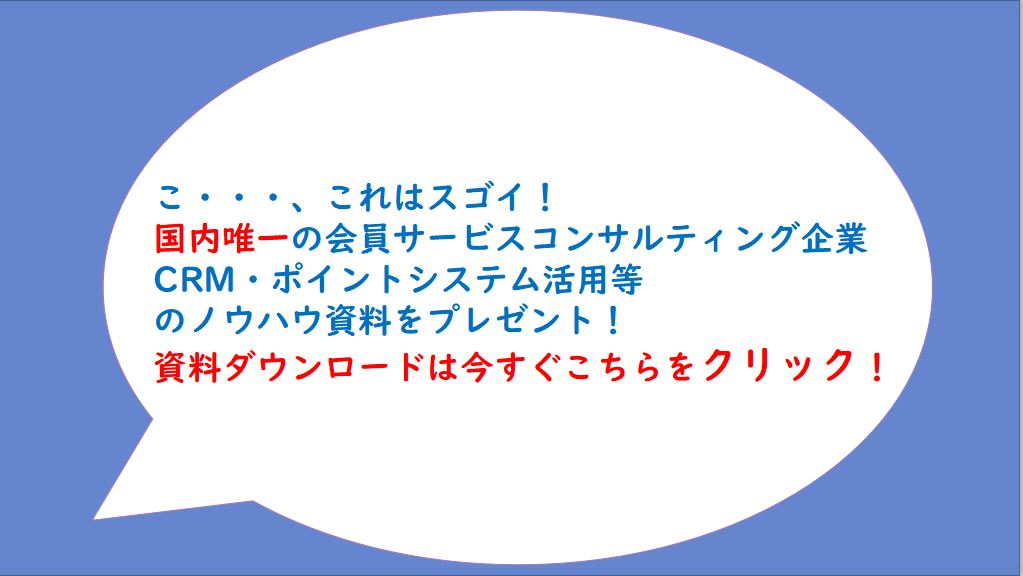
こんにちは。CRM/ポイントサービスコンサルティングのエムズコミュニケイト(2018年4月に大日本印刷グループよりMBO致しました)が運営するポイントマーケティングラボ編集部です。
こちらのサイト、ポイントマーケティングラボでは、企業・事業会社のマーケティング・販売促進の担当者・事業責任者の方々に向けて、ポイント制度の導入やCRMのノウハウについて、プロの視点から惜しみなく情報を発信して参ります。
是非ご参考にしていただければ幸いです。
それでは、以下から本題です。
今や日本の共通ポイント市場は戦国時代と言っても過言ではなく、どこへいってもポイントサービスが溢れている状態です。ポイントサービスの先駆者的存在のTポイントをはじめ、Pontaポイントや、dポイント、楽天ポイントなどが代表的でしょう。
また、最近大きく戦略転換を行っているヤマダ電機も、O2O戦略に力を入れて影響力を強めており、国内のポイント市場は選り取り見取りの状態です。
消費者からしてみると、複数のポイントを上手く使い分けることは少し難しい状況といえるでしょう。
顧客とのより強固な関係を構築していきたい企業にとっては、避けては通れないのがCRMであり、ポイントサービスは特に必要不可欠です。
今回は、各社が様々なポイント戦略を行っている中でも、特にご参考にしていただけそうな複数の事例をご紹介します。
共通ポイント系戦略事例:Tポイント、Pontaポイント

冒頭で申し上げたとおり、国内の共通ポイント市場は今まさに「戦国時代」です。
これまでは主流だった「1つの店舗で1つのポイント」という形も変わってきています。今は「1つの店舗で複数のポイント」が使えるので、顧客はどのポイントを使うのか選択できる時代になりました。当然各社の思惑や戦略は異なる一方で、O2O(Online to Ofline)の施策や、リアルとネットの両方をカバーしようというのはどの企業にも共通している傾向のようです。
【Tポイントの戦略】
会員数:約7,008万人(2023年3月時点)
TSUTAYAの会員からはじまったTポイントですが、現在はジャンルを問わず国をこえた普及が進んでいます。
Tポイントの現在の戦略は「Tライフドミナント」という方向性で展開しています。これは『日常生活の支出すべてにTポイントを』というコンセプトを掲げています。
これは、顧客との接触頻度や接触アクティブ率を重視しているわけではなく、日常の支出に関わる提携先がどれだけいるか、ということを指しているようです。
つまり、アクティブ率の低さや低額商品を扱っている提携先などは関係なく、あらゆる範囲の提携先を網羅していくという戦略です。
【Pontaポイントの戦略】
会員数:約1億816万人(2023年3月時点)
Pontaは、特にローソンの顧客を中心としたリアル店舗を展開してきました。
特に顧客の利用頻度が高いコンビニを取り込んだことが、Pontaポイントの協力な強みといえます。一方で、Pontaポイントは「ネット」に弱みを持っていました。
しかし、ネットに強いリクルートと統合したことで、業界構図を一転させることができました。
リクルートはホットペッパーグルメやホットペッパービューティなど、リアル店舗とのつながりもありつつ、ネット分野に強みを持っています。
現在は、リクルートIDとPonta会員IDを連携させることが出来るため、「提携店・街のお店」と「ネットのサービス」の両方でPontaポイントがたまる・つかえるようになっています。
https://point.recruit.co.jp/point/
リクルートのポイント戦略って?

リクルートは、ライフイベントのあらゆるシーンに登場するコンテンツとして、色々な事業展開を行っています。
美容や結婚、住宅や車の購入など、日常生活から人生まで、それぞれの重要なタイミングをおさえた事業を展開しているともいえるかもしれません。そんなリクルートのサービスの特徴は、すべてのサービスで共通IDを利用することができるという点です。
また、Pontaポイントとの連携により、リクルートIDで貯めたポイントをPontaポイントとしても使用することができるようになっています。もともとリクルートが持っていた媒体は、ポイント還元率が高かったので、使い道がかなり広がり利便性が高くなりました。
リクルートの狙いは主なものとして下記のようなものがあると考えられます。
1.ポイントによるリクルートサービス間の横断
先程も述べた通り、リクルートが運営しているサービスは、人生の大きなライフイベントに関わっているものも多くあります。
そのため、大半のサービスでは、1回で動く金額や影響力は大きいもののリピートしてもらう機会は少なくなります。すると、リクルートとしては運営サービス間をいかに横断してもらうかが重要になります。
そのきっかけとして、リクルートポイントという共通ポイントが もうけられているのです。
あるサービスやサイトの顧客が他のサービスを利用し、そこでポイントを上手く活用してもらうことがリクルートの狙いの一つでもあるのでしょう。
それでも、Pontaポイントと提携する以前のリクルートのサービスは、あまり頻繁にポイント利用する機会がありませんでした。
顧客がポイントサービスの価値を実感するシーンとは、購入頻度が高く単価は低い商品・サービスを購買する時といえます。したがって、日常的に利用しやすいPontaポイントへの交換は大幅に利便性を向上させています。
2.リクルートのポイント原資は、外部調達がメイン
ポイントの流通量を増やせば増やすほど、リクルートサービスを利用する機会は相乗効果的に増えることが期待されるため、リクルートとしてもポイント流通量をある程度確保したいというのは当然のことです。
そこで、重要なポイント原資となるのが、リクルートカードとAirレジとAirウォレットです。
なかでもリクルートカードは重要なポイント原資で、リクルートのサービス利用を介さずにポイント原資を調達することができます。また、リクルートカードは年会費無料でポイント還元率1.2%と還元率が高めに設定されているので、利用者にとってもお得感が高い仕組みとなっています。
このようにメリットを多く提供していることにも、リクルートの狙いが見えつつあるともいえます。
3.AirレジとAirウォレットでリクルートポイント経済圏拡大の目論見
2013年にスタートした「Airレジ」は、チェーン店ではなく小規模な店舗向けとして生まれた店舗用の無料POSアプリです。
小規模店舗にとって、従来のPOSレジの導入コストは高く、負担が大きいとされていました。そこで、ネットにつながるiPadさえあれば無料で使えるAirレジが提案され、拡大を続けているようです。
そして「Airウォレット」というサービスは、Airレジと連携して空席情報やクーポン情報を顧客へ発信したり、顧客側はポイントを貯めたり使ったりすることができるものです。
こういったシステムとリクルートポイントの連携も視野にいれ、リアルの世界にさらに「リクルートポイント経済圏」に取り込んでいくことが期待されているのではないでしょうか。
顧客の購買データを取り込み蓄積することにより、さらに顧客に寄り添うパーソナライズしたサービスを提供できるようになるメリットを店舗側に訴求していくことも考えられるでしょう。
https://recruit-card.jp/?campaignCd=crda0001
ヤマダ電機のポイント戦略って?

ヤマダ電機も、来店してくれた顧客のロイヤルティーを高め、来店率を上げることを目的にポイントサービスを展開しています。
2010年からは、携帯電話・スマートフォンアプリでのバーコード表示を通じたポイント付与システム「ケイタイde安心」を取り入れ、現在は「ヤマダデジタル会員」に名称を変更して提供しています。
「ケイタイde安心」を積極的に取り入れ始めた背景としては、「来店ポイントの付与」にあるとされています。
ヤマダ電機では、一人で複数枚のポイントカードを使い、ポイントマシンを乱用する顧客が一時期問題となりました。そのような状況を防止するために、原則として一人一台が前提となる携帯電話・スマホでのアプリのみでしか来店ポイントが貯められないようになったようです。
それを皮切りに、ヤマダ電機は「オフラインtoオンライン(O2O)の入り口」の戦略に力を入れ始めたとも言われています。
ttps://www.yamada-denkiweb.com/info/wcontents/digital-kaiin.html
「ヤマダデジタル会員」の安心サービス・お得な特典
安心サービス
- デジタル会員証
- 電子保証書と購入履歴
- スマホタッチで口コミ・在庫確認
- 毎週更新WEBチラシ
- 店舗検索
お得な特典
- ヤマダ会員限定値引き
- アプリ限定お得情報
- お誕生月特典
- ポイントバックゲーム
https://www.yamada-denkiweb.com/info/wcontents/digital-kaiin.html
楽天のポイント戦略って?

インターネットの分野で特に強い経済圏を築いている楽天ポイントですが、楽天ポイントの戦略とはいったい何でしょうか?
O2O(オフラインtoオンラインもしくはオンラインtoオフライン)施策を本格化させたい楽天は、2014年以降リアル店舗でも楽天スーパーポイントを使える場所を作りました。
すでにTポイントやPontaポイントがしのぎを削っている中、楽天ポイントの注目された点は圧倒的な会員数を誇る楽天会員をどのようにリアルに送客するかでした。
また、すでに主要企業はTポイント陣営やPonta陣営におさえられていて、相乗りはしない「1業種1社」という暗黙の了解をもっていました。
その理由としては、同じ業界の企業間はそれぞれ競争しているので、どこでも入れるようにすると誰も加盟してくれない、からです。
また、ポイント運営側にしてみても、同じ店舗に複数のポイント陣営が入っていると、自社のポイントが顧客に選ばれなくなり、とポイントの利用はおろか、消費者の情報も手に入れることができません。
そこで考えられたのが、「楽天チェック」です。
楽天チェックは、その店舗に訪れてアプリにチェックインした場合、来店ポイントとして楽天ポイントが獲得できサービスです。店舗へは、国内トップクラスの会員数の楽天会員を送客できるというメリットを訴求し、システム導入を促しています。
そして、この楽天チェックであれば、すでに他のポイント陣営が入っていても、「かぶることがない」のが大きな特徴といえるでしょう。というのも、TポイントやPontaポイントはそもそも会計時に加算されるポイントですが、楽天チェックは「来店ポイント」なので、まったく毛色が違うのです。
顧客は来店時には楽天ポイントを貯め、会計時にはTポイントやPontaポイントを貯めることが可能となります。また、店舗側もあらゆる陣営の顧客が見込み顧客になるので、損は少ないと訴求できます。
こういった、今までの「1業種1社」という常識を破った仕組みを楽天が取り入れることで、これからのポイント陣営の動きはますます激しくなっていくことでしょう。
個別ポイント系戦略事例:JRE POINT

共通ポイントは、いずれも大手のプレイヤーがしのぎを削っている中、これからポイントサービスの導入を検討する際には、その共通ポイントの加盟店もしくは提携先としてやっていくしか道はないのでしょうか?
いえ、そんなことはありません。共通ポイント戦国時代でも、敢えて自社ポイントにこだわる企業や、すでにある自社ポイントをサポートするツールも登場しています。
【JRE POINT】
これは、JR東日本が2016年2月からスタートした、新しいポイントサービスです。
自社ポイントといっても、JR東日本グループ内で利用できるというもので、JR東日本の鉄道を使う顧客向けのサービスです。
「えきねっと」と「JRE POINT WEBサイト」のそれぞれで会員登録を行い、えきねっとに会員番号を連携させる事でポイントを貯めたり、使ったりすることができます。
戦略としては、いままでJR東日本グループの店舗を利用していた顧客に対し、ポイントの利便性向上をもたらし、その上で新規顧客獲得も目指すという方向のようです。
人々が利用する鉄道インフラであるため、その強みを活かした自社ポイント戦略といえるでしょう。
https://www.eki-net.com/top/point/
まとめ〜知っておきたい!あの企業のポイント戦略事例
共通ポイント市場での競争が激しさを増す中、自社ポイントならではの特徴を活かした戦略が、一層重要になってくるでしょう。
共通ポイントはビッグデータという強みはあるものの、各加盟店がフォーカスされることはなく、顧客の囲い込みという観点でいえば、効果が薄くなります。
今回は、リクルート、ヤマダ電機、楽天ポイントの3社を取り上げてみました。各社に共通しているのは、O2O施策に注力し始めている点でしょう。しかし、それぞれ各社の強みを活かした切り口で戦略が異なることがお分かり頂けたでしょうか。
どんな業態においても、オンラインとリアルのどちらかだけでは生き残りづらい時代になってきました。そういった中で、各社はどのような仕組みを顧客に提供すればメリットを感じてもらえるのか、より多様なシーンでサービスを利用してもらえるのか、という観点でポイント戦略を練っています。。
規模が違うにしても、こういったポイントは、自社でも参考にしたい点でしょう。
ポイントサービス導入をご検討の会社様は、弊社エムズコミュニケイトにご相談ください!
①国内唯一・取り組み実績(エムズコミュニケイト)
国内で唯一のポイントサービスに特化したマーケティングコンサル会社です。これまでのポイントサービスの導入・改善支援は300社以上あり、通販、小売り、サービス、金融、鉄道・航空、ガス電力など幅広い業界において実績があります。
※ポイントサービス導入改善に関する国内初の指南書を出版
②サービス設計からシステム導入・運用までワンストップ支援
顧客課題を解決するサービス設計からシステム導入・運用まで、ポイントサービスにまつわる業務全般をワンストップでご支援することが可能です。ポイントサービス戦略設計、システム構築、個人情報管理、運用支援、プロモーション、カード発行、コールセンター、ポイント交換商品の発送管理など上流~運用までを網羅的にサポート可能です。
③ポイントサービス運用に関する法的・会計面のサポート
ポイントサービスの運用に必要な法的(景品表示法)、会計面(2021年から上場企業に強制適用されるポイント会計)において十全なノウハウを保有しサポートします。
※ポイント会計についてはEY新日本監査法人への執筆協力で『ポイント制度のしくみと会計・税務』(中央経済社)を出版。
④中立性を加味したシステムベンダー紹介
ポイントサービスのコンサルティング支援にあたり、ポイントシステムベンダーについては、中立性を重要視しております。貴社のニーズにあったベンダー紹介および、システムのカスタマイズ提案が可能です。