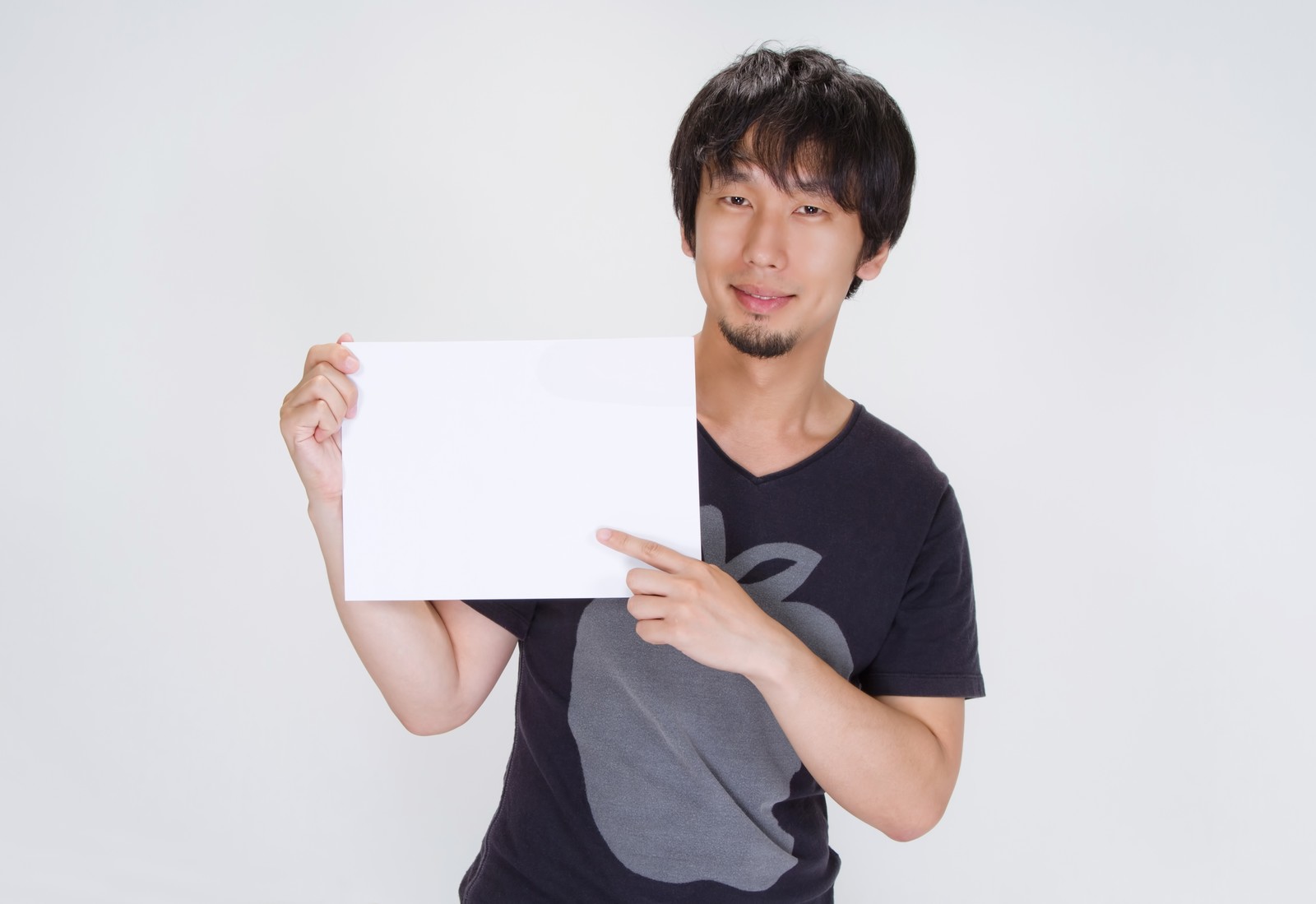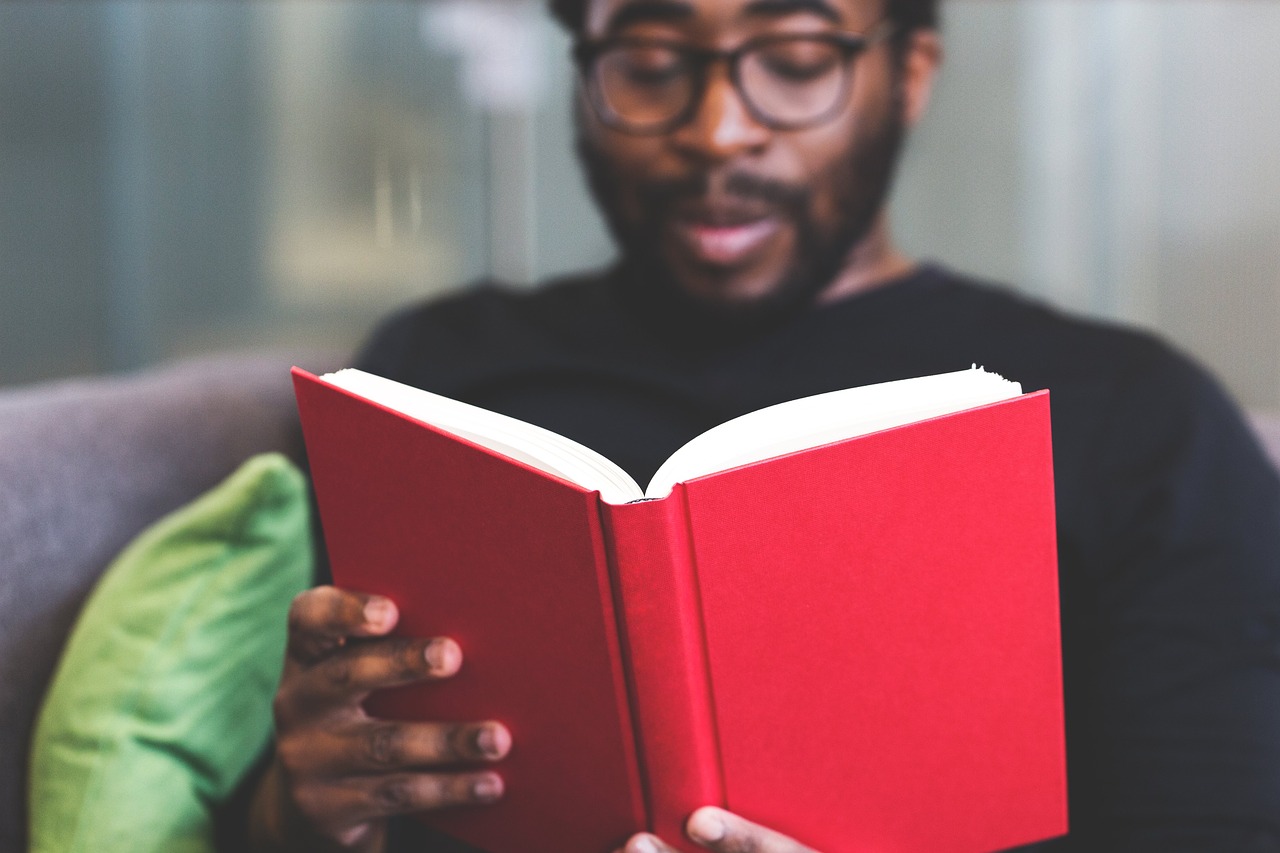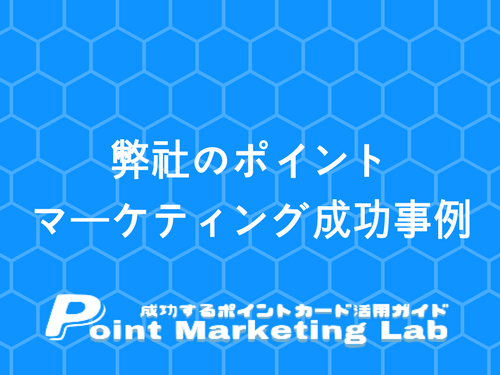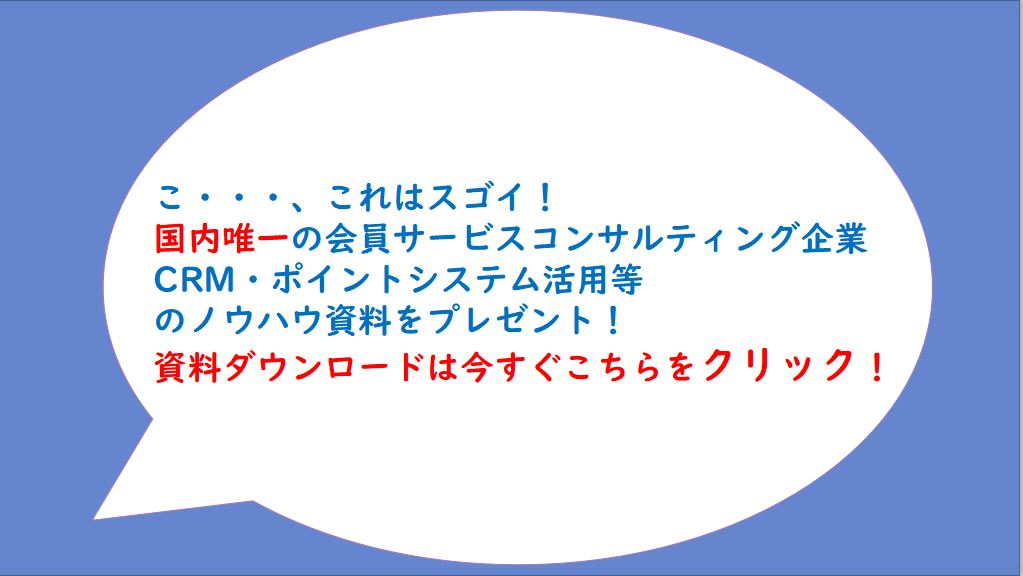エムズコミュニケイト 佐藤 信二
最新記事 by エムズコミュニケイト 佐藤 信二 (全て見る)
- 会員組織の立ち上げの効果を考える - 2017年8月29日
- マーケティングでは顧客情報の活用が重要です。 - 2017年8月1日
- プロ目線から考えるロイヤルカスタマーを重視すべき理由 - 2017年8月1日
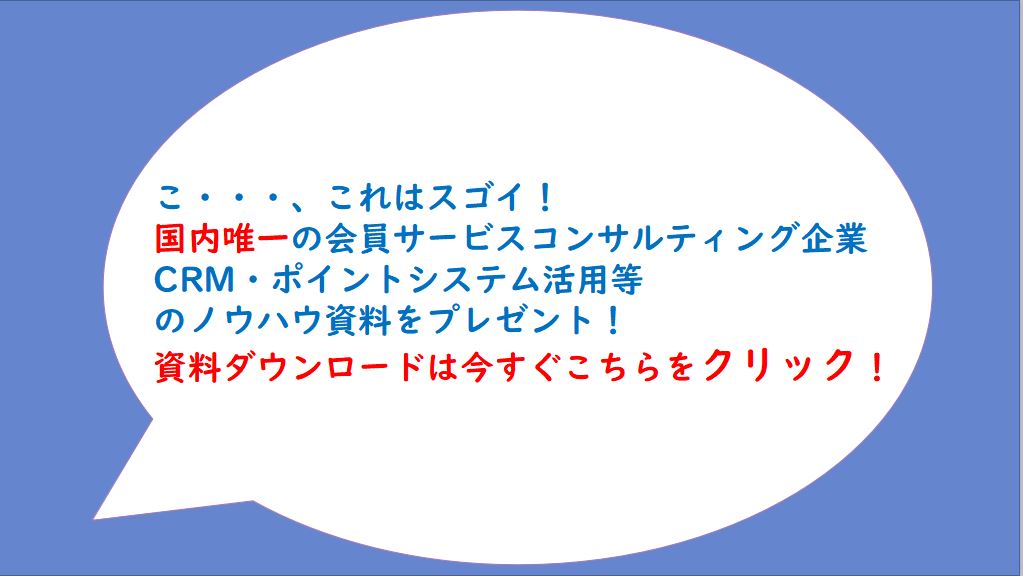
こんにちは。CRM/ポイントサービスコンサルティングのエムズコミュニケイト(2018年4月に大日本印刷グループよりMBO致しました)が運営するポイントマーケティングラボ編集部です。
こちらのサイト、ポイントマーケティングラボでは、企業・事業会社のマーケティング・販売促進の担当者・事業責任者の方々に向けて、ポイント制度の導入やCRMのノウハウについて、プロの視点から惜しみなく情報を発信して参ります。
是非ご参考にしていただければ幸いです。
継続的に利用している店でも、何かのきっかけで行かなくなってしまったことはないでしょうか?
今回は顧客が離反してしまったことから学び今後に活かす為の顧客離反の分析方法を一緒に考えていきます。
顧客離反の分析を考えてみる


顧客離反について、重要視している企業はどのくらいいるでしょうか?それに対して、何か対策をおこなうことや、原因について調査することはしているでしょうか?「去るもの後を追わず」としてしまって、何もしない企業も少なくないでしょう。離反防止の策はやっていても、離反後の分析についてはおろそかになっているのも珍しくありません。
「リピート率も優良顧客率も高いのに、売上が思うように伸びない」という難題に当たったことがありませんか?一概には言えませんが、この原因の多くでは顧客離反に大きく関係しているといえるでしょう。せっかくの優良顧客を育てても、何らかの理由で顧客が離反してしまい、顧客との長い関係性が上手く気付けていないのです。
顧客離反に対する対策や施策の有効性・重要性について、一度再確認してみましょう。顧客離反に対する施策は、離反する前とした後で大きく異なります。
よく提唱されているのは、「離反前」の防止策の重要性についてです。いずれの市場においても、新規顧客コストは高騰していて、獲得の難易度は年々増しているともいえるでしょう。ゆえに、各社厳しい闘いを強いられ、なかなかシェア拡大が難しい時代になってきているともいえるでしょう。このような市場の中では、『現状維持』が何よりも至上命題であり、現在の顧客をいかに逃さないかが重要性を増しているということになります。なので、簡単に言えば、「今いる顧客を逃してしまえば、新しく捕まえるのが大変だから頑張って繋ぎとめよう!」といったことでしょう。
それに対して、離反後に対する分析では、これとは何が違うのでしょうか?
最終的な目的は同じです。「今いる顧客を逃さないようにする」というところです。しかし、離反後の分析は顧客に対してアプローチすることではなく、全く性質が異なります。「なぜ離反してしまったのか」ということです。離反の原因を探ることは重要です。なぜなら、離反しないようにいくら施策を企業がおこなっても、『真の離反の理由』が分からなければ、結局顧客に想いは届かず逃げてしまう可能性が高いからです。「なぜ顧客は離反してしまったのか」と過去を反省し、受け入れることで、新たな離反顧客を防ぐのに大きな役割を果たすのです。
また、離反してしまう原因は、よくある「顧客満足度調査・アンケート」では分からないことが大半です。しかし、一度サービスや商品を利用している『経験者』なのです。にもかかわらず、何らかの理由で、リピートしなくなってしまったのです。
理由には、分析だけでは測れない個々の事情(引越しや子供の進学などの生活の変化)もあるので、一概に当てはめることはできませんが、ある程度の傾向を掴むことはできるでしょう。
顧客離反の分析方法


では、顧客離反に関する分析方法について考えてみたいと思います。顧客が離反する傾向や兆候、顧客離反率から何か分かることはあるのでしょうか?
まずは、顧客離反率とは何でしょうか?
顧客離反率というのは、顧客がある一定期間で、どのくらい離反したか示す割合です。当然のことながら、この割合は少ない方が良いです。それに対して、顧客維持率とは、顧客から、いかに契約解除されないか、いかにリピートされるか、いかに変わらない水準で受注できるか、ということです。つまり、顧客離反率と顧客維持率は同じ現象を別の視点から見ているだけにすぎません。
離反率の計算方法としては、単純です。例えば美容室だったら、同じお客さんが1ヶ月に1回来店するとして、年の始めの来店者300名のうち、年の終わりまで来店する人が120名とすると、顧客維持率40%、顧客離反率60%となります。
さて、このように顧客離反率を算出して現状を確認し、事実を受け入れることは大切ですが、次に重要となってくるのは、「どんな顧客が、どんな理由で離反するのか」というところです。
今回は、パターン検出分析を利用した分析方法を考えてみたいと思います。残念ながら、離反してしまった顧客がどんな行動をおこしていたか、ということに注目してみるのです。行動パターンを見極めることで、離反顧客の傾向を掴むことができます。
外食業界を例に考えてみましょう。
利用頻度はどうでしょうか?時間帯の変化、利用曜日や、利用する店舗数、訪問間隔・滞在時間などに変化はあったでしょうか?離反傾向のある顧客には、その企業に対して落としていく金額にも変化があるかもしれませんね。客単価にも注目してみるのも、指標の一つです。
また、注文内容やサービスの利用方法には何か変化があったでしょうか?クーポンサービス利用も積極的ではなくなってるでしょうか?
これらの行動が将来の離反に結び付くかどうかについては、それぞれの企業の状況により異なるので、一概には言えないかもしれません。ですが、分析をすることにより、一見離反とは直接関係なさそうな行動が実は離反の予兆などが発見できるかもしれません。さらにいえば、行動一つだけでなく、顧客の行動が複合的に組み合わさり、そのいくつかのパターンが「離反顧客」の特徴となっているかもしれません。むしろ、一つの特徴よりもより、離反する顧客に近づけるといったパターンもあるでしょう。こういった複合的な要素を見抜くためには、ツリー分析などが有効だといわれています。
【ツリー分析とは?】
分析手段の方法として用いられ、観察対象(今回の場合は顧客)のデータを、従属変数(今回の場合で言えば、顧客の行動)によって、木の枝のように分岐させて整理する手法のことです。データの分析・整理の際に、効率的な手段として傾向やルールをあぶり出すのに使われることが多いでしょう。ツリー分析では、視覚的に分析結果を把握できるとともに計算方法が比較的簡単で、モデル作成しやすいことが特徴とされています。
顧客離反を分析をどう活用するか


では、これまでの離反顧客の分析から、傾向がつかめたら一体これをどう活かしていけば良いのでしょうか?アプローチの方法を考えてみたいと思います。
離反顧客の傾向を知ることにより、離反防止策の対象となる顧客を定めることが可能です。
「離反しそうな顧客」にアプローチができる
まずは、なによりもこの対策のメリットが大きいでしょう。今までは、原因が不明であったのでいつの間にかある一定数の顧客が「いつの間にか離反していた」状態でしたが、分析結果により、ある程度の傾向がつかめているのであれば、その傾向に当てはまり始めている顧客は、「離反予備軍」とも言えるでしょう。そういった危うい顧客に対して、特別なアプローチができるのは、企業によってはメリットです。適切なアプローチをおこなえれば、その後の離反を防ぐことができるかもしれません。
やみくもにキャンペーンを行うよりも、的を絞って「より魅力度の高い」試みをスポット的におこなうことができます。これが意味しているのは、プロモーションの効率化にもつながります。
適切な顧客に、適切な形でアプローチして関係性を築くのは非常に大事なことです。
「誰(対象顧客)に対して案内を送るか」「何(商品/サービス、提案、インセンティブ、メッセージ)を送るか」「いつ(タイミング)送るか」「どのチャネルを通じて送るか」といったことを、いま一度見直す良い機会になるでしょう。
顧客離反の分析方法まとめ
今回は、すでに離反してしまった顧客の傾向を掴むことで、今後の顧客離反を改善を目指していこうとする目的を持つという視点でまとめてみました。
企業の中には、顧客ひとりひとりの購買行動をデータ化して持っていても、離反予兆の分析までは活用していない企業も多くみられます。このような企業は、離反を最小限に食い止めるための鍵をみすみす眠らせてしまっているのではないのではないでしょうか。
ポイントサービス導入をご検討の会社様は、弊社エムズコミュニケイトにご相談ください!
①国内唯一・取り組み実績(エムズコミュニケイト)
国内で唯一のポイントサービスに特化したマーケティングコンサル会社です。これまでのポイントサービスの導入・改善支援は300社以上あり、通販、小売り、サービス、金融、鉄道・航空、ガス電力など幅広い業界において実績があります。
※ポイントサービス導入改善に関する国内初の指南書を出版
②サービス設計からシステム導入・運用までワンストップ支援
顧客課題を解決するサービス設計からシステム導入・運用まで、ポイントサービスにまつわる業務全般をワンストップでご支援することが可能です。ポイントサービス戦略設計、システム構築、個人情報管理、運用支援、プロモーション、カード発行、コールセンター、ポイント交換商品の発送管理など上流~運用までを網羅的にサポート可能です。
③ポイントサービス運用に関する法的・会計面のサポート
ポイントサービスの運用に必要な法的(景品表示法)、会計面(2021年から上場企業に強制適用されるポイント会計)において十全なノウハウを保有しサポートします。
※ポイント会計についてはEY新日本監査法人への執筆協力で『ポイント制度のしくみと会計・税務』(中央経済社)を出版。
④中立性を加味したシステムベンダー紹介
ポイントサービスのコンサルティング支援にあたり、ポイントシステムベンダーについては、中立性を重要視しております。貴社のニーズにあったベンダー紹介および、システムのカスタマイズ提案が可能です。